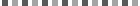
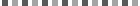
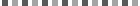
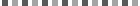
「よっ……っと」
頭に血ののぼった危険なゼクセン騎士二人から、屋根へと逃げた俺は、今度は屋根づたいに城の裏手へやってきていた。
そこには、どういうふうにこうなったかは不明だが巨大な帆船が突き刺さっていて、屋根から甲板に降りることができる。
降りてからきがついたんだが、どうやらここも居住地として使っているらしい。建築法とか、強度とか、そういうのは……多分どうでもいいんだろうな。
城の探索は面白そうだったが、また騎士団の連中みたいにからまれちゃかなわない。俺は人目を避けるように、甲板を人気のないほうへと歩いていった。
そのときだ。
ざあっ、と俺の上空を鋭く風が吹いていったのと同時に、足下が翳った。
「っ?!」
ぶうん、という耳障りな低い音が俺の耳をつ突き刺す。武器を構えて振り仰いだ先には、巨大な甲虫が五月蠅く羽音を響かせながら浮かんでいた。
「っ……な……んだ?」
鳴き声だろうか? ぎちぎちとやはり耳障りな音をさせながら、カブトムシのような、セミのようなその虫は俺を伺っている。
こんなに人の多い城だというのに、何故モンスターが?
戦争中のくせにのほほんとしたこの城の雰囲気のせいで見張りまでぼけたのだろうか?
俺は巨大な虫を刺激しないように、そろそろと手を動かした。確か、ジャケットの内ポケットに閃光弾が一発入っていたはずだ。どこまできくかわからないが、これで目くらましをしたあとに、屋根の下に逃げることにしよう。
ゆっくりと、ゆっくりと俺は手をジャケットにいれる。
閃光弾に手が届いた、と思った瞬間、巨大虫はぶうんっとこちらに向かってきた!
「くっ!」
間に合うだろうか?
思いっきり後ろに跳び、閃光弾を握る。だが発火させる直前、俺と虫の間には何故か頭上から巨大な炎が割って入ってきていた。
「うわぁっ!!」
『ギギィーーッ!』
俺と虫の叫びが重なる。今日二回目、空を見上げると今度は虫よりも更に巨大なものがいた。
「……? ど、ドラゴン?」
大きな羽、長い首、白銀という珍しい色をしているが、間違いなくドラゴンだ。
一瞬、モンスターが増えたのかと思ったがそうじゃなかった。目を凝らしてみると、ドラゴンには鞍がつけられ、三人の人間が乗っていた。
「ルビ! ナッシュさんにじゃれるのはよしなさい!」
乗っていた三人のうち、青い服を着た一人が叫ぶ。
ルビ? ……あの虫、名前あるのか?
驚いて見ていると、虫はその声に反応してか、ぎちぎちと不満そうな音をたてた。すると、高度をだいぶさげたドラゴンからその青い服の青年が降り立ち、慣れた様子で虫にまたがる。
え……またがるの? それ??! っていうか乗り物なの?!
俺が呆然としていると、青い服の青年は、虫にまたがったまま礼儀正しくハルモニア式の礼をした。
「申し訳ありません、ナッシュさん。私の躾がいたらないばかりに不快な思いをさせてしまいました。このようなことがないように、厳しく叱りますので」
「あ……ああ、いいよ。実害は……なかったし」
「本当にすいません! では! ルビ! 行くぞ!!」
パン、と軽く頭を叩いてやると、虫は青年の命令通り宙に舞い上がった。そして、城のほうへと飛んでいく。
「……あれも、まさか戦力?」
確か、随分前に叩き込まれた地理の授業で、グラスランドとの境界付近には虫を操り空を飛ぶ民族の話を習ったような気がする……が。いや、いいや。なんかどうでもいいことのような気がする。
現実逃避をしながら、頭を振っている俺の前に、ばさりとまた羽音をさせ、さっきのドラゴンが降り立った。
「ナッシュさん、災難でしたね」
顔をあげると、快活そうに笑いながらドラゴンの背に乗っていた青年が声をかけてきた。
歳は二十代後半くらいだろうか? 竜洞騎士団特有の額飾りをつけた、大柄な青年だ。しかし、大柄だからといってむさ苦しいわけではない。手足が長く、精悍な顔立ちをしているせいか、結構な男前だ。
「ありがとう、助かった」
俺が礼を言うと、青年は楽しそうに笑いながら降りてくる。そして、もう一人竜に乗っていた小柄な人影も。
「ナッシュさん、本当に変なのにばっかり好かれるよねー!」
無邪気に笑いながら、俺を見上げるその人物は、金髪のこれも結構かわいい女の子だった。多分歳は十五、六。笑った時の八重歯と、射抜くようなルビーアイが印象的で、青年と同じ竜洞騎士団の額飾りをつけている。
青年は、握手を求めるように手を出しながら、困ったような、笑いたいような顔になった。
「えっとナッシュさん、お久しぶりと言ったらよいのでしょうか? 僕はフッチ、といいます?」
「え? 久しぶり? 俺、今15年分記憶が飛んでるんだけど?」
俺が驚くと、フッチは苦笑する。
「その15年くらい前に一度お会いしているのです。うーん、ぎりぎりで会ったことがあるかどうか怪しいのですが……クリスタルバレー近くで、一緒にはぐれ竜退治をした子供のことは、記憶にないでしょうか?」
クリスタルバレー、はぐれ竜と聞いて、俺はやっと思い出した。俺にとっては結構最近のことだ。
「ああ! あのチビ竜連れてた少年か! そうだ思い出した! 確かにフッチっていう名前だったな。ってことは……あのチビ竜がこいつか?」
俺は、おとなしく人間達のやりとりと見守っていた白銀の竜を見上げた。俺が思い出したのがわかるのか、竜は俺に顔をすり寄せてくる。
「でっかくなったなあ……今の俺がオヤジ呼ばわりされるのも当然かあ」
俺の記憶のチビ竜は、まだまだ子犬くらいの大きさで飛ぶこともままならなかった。フッチなんかは本当に華奢で、つつけば折れそうな感じだったし。それが、今俺の目の前で穏やかに立っているでかい兄ちゃんになったのかと思うと、年月ってものはすごい。むごいとも言うか。
「そうだ、で、この子は誰だ? あの時は連れてなかったと思うが……」
記憶にない金髪の少女を指して、俺はフッチに訊ねた。
「この子はシャロン、竜洞……」
「フッチの彼女でーっす!」
フッチの言葉を元気よく遮ったシャロンの台詞に、俺とフッチは同時に絶句した。
「……なかなか若い彼女だな」
「嘘です! 嘘!! シャロン! たちの悪い冗談もいい加減にしなさい! もう……彼女は同じ騎士団の騎士見習いです! 無理矢理ついてきたので、手伝いをさせながらいろいろ教えているところなんですよ」
「いーじゃんフッチー! これくらい!」
「だめだ!」
シャロンの不満を、フッチは頭ごなしに押さえつける。
はー、たちの悪い冗談ねー。の、割にはフッチ、君の動揺は激しいし顔もかなり赤いと思うんだけどさ。……まあいいか。他人の恋愛に首をつっこむもんじゃない。
「ねーねーナッシュ、フッチってひどいと思わない? たかが13歳差だっていうのに力一杯否定するの」
「……人によっては気にするんじゃないのか?」
「えー! ナッシュだって歳の離れた奥さんいるくせにー!」
「はぁ?!」
「馬鹿、シャロン!!」
慌ててフッチがシャロンの口を押さえたがもう遅い。俺は、シャロンの言葉に呆然と立ちつくした。
……奥さん?
誰に奥さんがいるって?
まさか俺じゃないよな?!!
生まれてこの方、ふられまくりの遊ばれまくりで、しかも家族の家庭まで壊した俺に、奥さん?
…………奥さん?!
「フッチ……?」
俺が助けを求めるようにフッチを見ると、最初以上に困った顔でフッチは微笑んだ。
「とても……言いにくいのですが、実はナッシュさん、このお城では『愛妻家』として有名なんです」
「あ、愛妻家ぁー?!!!!」
頭を殴られたような衝撃に、俺は叫ぶしかなかった。
深夜。
俺はやっとのことでたどりついた自分の部屋のベッドに倒れ込んでいた。
「疲れた……」
つぶやくその声も力無い。
フッチに衝撃の事実を知らされたあと、俺の『カミさん』とやらは誰なのか調査に出かけ……収穫を得られず力尽きて部屋に舞い戻ってきたのだ。
どうやら、スパイとしての習性は15年たってかなり磨きがかかったらしく、城内で有名人のくせに15年後の俺のプロフィールは、「奥さんもちのハルモニア人」であることしかわからなかった。
スパイとしては正しいはずなのだが、今の俺には迷惑な話だ。
しかも、情報収集のためと城に戻れば、変な仮面の男に引っ張られて舞台に乗せられるし(ジュリエットがジーンさんなのは嬉しいが、衛兵がゼクセン騎士団なのはどういうイヤガラセだ)、酒場に行けばカラヤの女傑に捕まってしこたま酒を飲まされ、何故か女の子達には「手品やってー」とせがまれる。
これで疲れないほうがおかしい。
まあ変に探ろうとしなくても、数日の後には戻るみたいだから、あまり考えなくてもいいのかもしれないが。
「寝るか……」
考えるのが面倒になって、俺はジャケットを脱ぎ始めた。
もう寝よう。多分この頭じゃこれ以上は考えられない。
しかし、ジャケットを脱ぎ、手袋を脱いだところで俺はぎくりと体を強ばらせた。
ここに来てから初めて脱いだ手袋。覆うもののなくなった俺の左手の薬指には白銀に光る指輪がはまっていた。
「……嘘だろ?」
俺は指輪を見つめる。
年期のはいったその指輪は、当然今の俺の指にはなじんでいない。だが、15年後の俺にはきっとなじんでいたのだろう。跡さえついていたのかもしれない。
外して、指輪の内側を見ると十年前の日付が小さく彫り込んであった。
「……っ!」
俺は指輪を手に握り混んだ。
城内を聞き込んで、俺のカミさんのプロフィールが全く出てこなかったとき、真っ先に考えたのが「嘘」だった。今回仕事で一番最初にちかづいたのはあの強力な護衛のいるゼクセン騎士団長様。きっと独身の男では信用されない。だから、誰かをモデルにして嘘の経歴をでっちあげた。クロービス、なんて偽名まで使っているのだ、可能性は高い。
そう、思って流そうと思っていたのに。
俺には、いたのだろうか?
過去のしがらみを捨てて、共に生きたいと願う相手が。
そして共に生きたいと願ってくれる相手が。
ベッドにつっぷすると俺はまた呻いた。
誰だ?
俺が誓った相手は一体誰なんだ?
答えのない問いがぐるぐる回る。
今の俺が会ったことのある女なのか、会ったことのない女なのか。
相手が誰なのか今の俺には想像が……いや
俺は体を起こすと頭を振った。
いや、いることにはいるのだ。「カミさん」という話を聞き、その女がどうやらかなり気の強い女だという話を聞いてから、ずっと奥さんではないかと思っている女が。
だがそれは心当たりというよりは、こうだったらいいのにという願望に近い。
アイツが奥さんだったら。
共に生きているのがアイツだったら。
それはきっと幸福だろうと思うが、俺は昔彼女に思いっきりふられている。そんな女を想像するなんて、女々しいにも程がある。
「シエラ……」
「なんじゃ」
思わず出た言葉には、返答があった。
「え? えええ?」
後ろを振り向くと、窓辺に女が一人座っていた。
いや女と言うよりは少女と言ったほうがいいのか。月光に照らされた淡い髪の色は輝く白銀。血のようなルビーアイは見た目にそぐわない程の落ち着いた光をたたえている。服装こそ、少し違ってはいたけれど、間違いない、シエラだ。
幻のように美しいその少女の存在を確かめるように手を伸ばすと、少女は艶然と微笑んでその手を握り替えしてきた。
柔らかくて、小さくて暖かな手触り。
「シエラ?」
「なんじゃ」
問いかけると、シエラは答える。
抱き寄せると、彼女は抵抗なく俺の腕の中に収まった。
「シエラ、なんでここに? あんたも戦争に参加してたのか?」
「参加はしておらぬよ。ただでさえこの戦争は真の紋章が関わりすぎておる。真なる月の紋章の主たるわらわが仲間におっては力が集まりすぎるからのう」
「じゃあ何故」
俺は期待してしまう自分の心を必死で抑えた。
まさか、まさか彼女は。
シエラは笑いながら左手で俺の頬をなぞった。その手をとらえると、そこには俺が持っていたのと全く同じデザインの白銀の指輪がある。
「妻が夫に会いに来るのに、何の不思議があろうぞ」
「……あんたが俺の奥さんっていうのが一番不思議だよ」
俺はぎゅう、とシエラをだきしめた。これが夢じゃない、って実感するために。
「おや不満かえ?」
シエラはくつくつと笑う。俺が不満になんか思ってないってことくらいお見通しのくせに。
「なわけないだろうが! 俺は……今の俺にカミさんがいるって聞いたときからずっと……その、あんたがカミさんだったら……っていうかあんたじゃなきゃ嫌だって思ってたんだ!」
言うと、シエラは満足そうにまた笑う。
こういうこと言わせて満足するあたり、15年たっても性格は変わってないみたいだな。
俺はシエラを抱きしめたまま、初めて15年後の俺に感謝していた。
経緯はわからない。きっと苦労したんだと思う。けれど、この女をつかまえたなんて、でかした俺!!
「シエラ……」
キスをねだるように顔を近づけると、シエラはくすぐったそうに首をすくめる。
「なあシエラ、俺が若返ってからも、奥さんはあんたがいいって思ったこと、ちょっと嬉しかったんだろ」
シエラの上機嫌の理由を見つけてそう囁くと、軽く頬をつねられた。
「内緒じゃ」
くすくすと笑うシエラの極上の花のような唇にキスしながら、俺は珍しく訪れた幸福に浸ることにした。
翌日。
コンコン、というノックの音で俺は目をさました。
「ん……?」
体を起こして辺りを見回すと、ビュッデヒュッケ城の簡素な部屋が見えた。体を見下ろしてみると、22歳の記憶を持った22歳の俺の体がある。
やれやれ、一晩寝れば治る……なんて、風邪みたいにはいかないか。
俺は隣で寝ていたシエラを隠すように布団をかけてやると、ズボンだけひっかけて戸口へ向かった。
「誰だ?」
ドアを開けると、ゲドと、それからゼクセン騎士団長のクリスが立っていた。
「おはよう、どうしたんだ? こんな朝はやく」
「そんなに早くもない。昨日は引っ張り回されていたようだし、見舞いに……と思ったのだが、その必要はなかったみたいだな」
言いながら、ゼクセン騎士団長様は何故か不快そうに顔をゆがめた。
「え? 何何?」
「若返ったその日にそれか、このナンパ男」
言い捨てるが早いか、クリスは踵を返して立ち去っていく。
「なんだよそれは! クリス? おいクリス!!」
わけがわからず叫ぶ俺に、ゲドは無言でとんとん、と首筋を叩いた。
「何?」
「……痕」
言われて、俺は気がついた。俺はズボンをひっかけただけの、上半身裸。そこには昨日シエラにつけられた噛みあとやらキスマークやらがいろいろとついている。
しまった……。
こ、これじゃ事情を知らない人間には「記憶をすっとばした当日に、早くも女を引っかけて部屋に連れ込んだ男」にしか見えない。
「ちょっと待ってくれクリス! これはカミさんのーー!」
しかし、カミさんの詳しい説明のできない俺の言葉にどれだけ説得力があるのか。
俺はクリスを追いかけながら頭を抱えた。
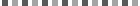
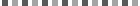
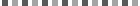
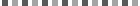
はい、いかがでしたでしょうか。
結局もとにもどってないですが、一応話はこれで終わりのつもりです。
朝、もとにもどって終わりでもよかったのですが、
それじゃありきたりかなーということで
最後でちょっとぷち不幸。
まあナッシュがそう簡単に幸せにはなれませんから
>前編に戻ります
>メニューに戻ります