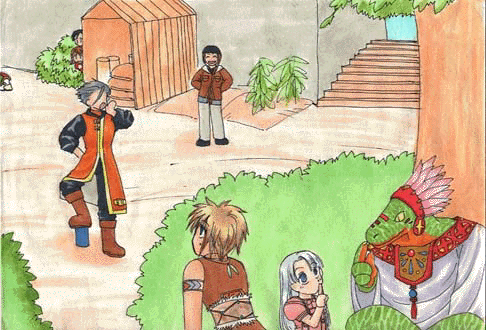
城の裏手。裏と言う割に日当たりのいいそこは、メイミというコックがやってきてからレストランが開業されていた。雰囲気もよく、料理もおいしいそこは、城の住人のよき憩いの場となっている。いつもならば、誰もが明るい気分で食事をしているそこで、甲冑姿の騎士が二人、最高に不機嫌な顔で座っていた。
その二人のテーブルの上に、ファイルがどさっと投げ出される。次いで、空いている席にサロメが座ってきた。
「随分暗いですね、レオ殿、ロラン殿」
「まあな……」
その巨体を丸めるようにして座っていたレオは低い声で返事をする。ロランも、気のない返事を返してきた。
「クリス様は?」
サロメは辺りを見回した。あのあと、結局クリスの身柄は妥当なところで騎士団が預かることになり、サロメは会議の間、パーシヴァルたちに任せることにしたのだ。だが、レオとロランの近くにはいない。
サロメの問いに、レオは畑のほうを指差した。そこでは、小さなクリスを中心にシャボン、メルヴィル、アラニス、エリオット、そしてコロク達風呂敷犬がいっしょになって遊んでいる。その輪の中に、甲冑を外したパーシヴァルが保護者よろしく加わっていた。
「お二方は、加わらないので?」
サロメが不思議そうに聞くと、レオはますます体を丸めた。ロランもため息をつく。
「……親しみを込めて、笑いかけてさしあげたら、泣かれたのだ」
レオの心底悲しそうな声音に、サロメは吹き出しそうになるのを必死にこらえる。
「私は、泣かれはしなかったのですが、ゲームの説明をしているうちに飽きられてしまいまして……」
「一回のプレイに三日かかるゲームをしようというのが、そもそも間違っておるのだ」
「そうでしょうか……?」
ロランは不思議そうに首をかしげる。サロメは、なんとかこみ上げる笑いを飲み下した。
「そういうことなら、私もあまり近づかないほうがよいでしょうな」
眉毛の薄い自分の顔が、子供受けしないのはサロメとて重々承知している。
「パーシヴァルの奴は、随分と得な性分をしてるよな」
レオが悔しそうにそう漏らす。確かに、とロランはうなずいた。
田舎育ちのパーシヴァルは、簡単にできて子供うけする遊びをいろいろと知っていた。それに加え、ゲーム中子供があきないようにわざと負けてやったり、子供達を調整してやるだけの心配りもできる。
「騎士団をやめても、保父で食べていけそうだ……」
「その意見には賛成じゃな」
誰に聞かせるわけでもないサロメの言葉に、子供の声が相槌をうった。
「わっ、ビッキー?」
いつの間にそばに来たのか、小さいほうのビッキーがテーブルの脇に立っていた。少女は、落ち着き払った態度で騎士達を見上げている。
「クリスが子供になったと聞いたから、様子をみにきたのじゃ」
十六歳のビッキーよりもなぜか数段頼りになる少女は、遊ぶクリスに目を移す。サロメは少女を見下ろした。そういえば彼女も魔法使いだ。
「ビッキー、貴方の見立てではどうです、戻れそうですか? エステラには「王子様のキスで魔法がとける」などと御伽噺のようなことを言われたのですが」
「……口付けには魔法の力が宿っておるから、あながち嘘ではないが……。エステラも相変わらずじゃな」
ふう、とビッキーはため息をつく。
「安心せい。ロディとビッキー程度の魔法ならば、複合したとしても、大した効果はない。もってせいぜい三日というところじゃろう。そのうち勝手に元に戻る。エステラが余裕で嘘をついているのもそのことがわかっているからじゃ」
なんだ、とレオがほっとしたため息をついた。
「それならそうと早く言ってくれればいいものを……」
「それを素直に言う人だったら、苦労はしませんよ」
サロメもやっと安堵の息を吐く。
「ビッキー、ありがとう。これで少しは肩の荷が降りましたよ」
「ビッキーのやったことがそもそもの原因じゃからな。礼はいらん」
そう言うと、少女はまたとことこと歩いてどこかへ行ってしまった。残された騎士達は、やれやれ、と顔をほころばせる。それから、ロランがぽつりとつぶやいた。
「七歳児が一番頼りになるこの城の魔法戦力って一体……」
サロメとレオは何も答えなかった。
「もうっ、いいかげんにしてよねっ!」
アラニスが、地面に転がる人物に怒鳴りつけた。
「本当にしつこいんだから!」
シャボンがさらにタンバリンでどつく。縛り上げられ、地面に転がされたまま、その人物はいやいやをするように首を振り回した。
「私はただ一緒に遊びたいといっただけですほほ〜〜〜〜〜〜〜〜い。
それだけで縛るなんてひどいですほ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜い」
「ギョーム殿、あなたのそれは、犯罪です」
クリス達が仲良く遊んでいたその平和な光景に乱入してきた変態、ギョームを投げ飛ばし、縛り上げたパーシヴァルが、本気の形相で相手を睨みつける。
「それをいうなら〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
二十歳をすぎて一緒に遊んでる貴方も犯罪で〜〜〜〜〜〜〜〜す。
ほほ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜い」
ごす。
クリスの白い手がギョームの眉間を直撃した。
「パーシィを悪く言っちゃだめ!」
若干五歳とはいえ、華のような美少女に構われたのが嬉しかったのか、ギョームはその体勢のままうひひひひひひひと笑い始めた。ひっと小さく悲鳴をあげてクリスがあとずさる。
「クリス様、お下がりください。このような者に触れたらお手が汚れます」
パーシヴァルはよいしょ、とギョームの襟首を掴むと引きずり始める。
「レオ殿たちに頼んで牢屋にいれてもらってきます。聖ロア騎士団の方々、クリス様のことを、見ていてあげてくださいね」
「はい、命に代えてもお守りします」
元気のよいメルヴィルの返事に、微笑みを返すと、パーシヴァルはよく分からない叫び声をあげるギョームを引きずって歩いていった。幸い、レオたちはそばにいるし、牢屋も近所だ。すぐ戻ってこられるだろう。
「やっぱりパーシヴァル様ってかっこいいなあ……」
エリオットがその後姿をうっとりと見つめた。
「剣の腕だけじゃなく、乗馬の腕前もすごいんだってさ。僕もあんな騎士になれたらいいなあ……」
メルヴィルもまたうっとりとつぶやく。
「メルヴィも、騎士様になるの?」
見上げたクリスに、メルヴィルは笑いかける。
「まだまだ先の話だけどね。来年になったら、士官学校の入学試験を受けて、それからだから。本当にずっとさき。それでもなれるかどうかわからないけど」
「そうなんだ……」
クリスがしゅん、とうなだれた。アラニスがその顔を覗き込む。
「どうしたの? クリス」
「メルヴィでもなるのが大変なのに……クリス、騎士になれるかなあ?」
「クリス、騎士になりたいんだ?」
シャボンが言う。
「うん。大きくなったらお父様やパーシィみたいな騎士になるの!」
「ほう、そんなころからそのようなことを考えていたのか」
突然、彼らの周りが翳った。見上げると、赤い羽根飾りをつけた巨大なリザードと、黒い鱗のリザードが立っている。
「……!」
子供達は言葉を飲んで立ち尽くす。クリスに至っては泣く一歩手前である。クリス以外の四人は、リザードが決して怖い人種でないことを知っている。しかし、同時に彼らがクリスに敵意を持っていることも知っていた。
「デュパ殿、シバ殿!」
パーシヴァルが牢屋のほうから、全速力で走ってきた。おもしろくもなさそうにデュパが顔をそちらに向ける。
「どうされたのですか? しばらくはそっとしておくという約束では」
「ああ、手出しはしないと約束はした。だが、私たちには、銀の悪魔を見定めることも必要だ」
パーシヴァルは唇をかんだ。話の筋は通る。彼らが今のクリスの状態をきちんと確認しておくことは必要だ。だが、このように突然来られては困る。現にクリスはおびえきっていた。人の間で育った幼児が、何の予備知識もなくリザードと相対すればこうなるのが普通だ。
「しかし……」
「お前は黙ってろ」
シバがパーシヴァルの肩をどん、と押しのけたときだ。
「パーシィにひどいことしないで!」
クリスが叫んだ。そして、リザードたちにアメジストの瞳をまっすぐ向ける。
「パーシィにひどいことしたら、許さないんだからあ! だいたい、お名前も名乗らないで、失礼よ、あなたたち!」
一気にまくし立てると、クリスはデュパを睨みつけた。パーシヴァルは背筋の凍る思いて二人を見つめる。これは、同盟決裂覚悟か、とパーシヴァルが剣に手を伸ばそうする。
しかし
一瞬後、デュパは腹を抱えて大笑いを始めた。
「は、はははははははははっ。なりはちいさくてもやはりあいつだな。気の強さは一緒だ!」
そう言ってげらげらと笑いつづける。
「パーシィ……これって……」
不安そうにパーシヴァルを見上げるクリスに向かって、デュパは手を差し出した。
「失礼したな。私はデュパ。リザードクランの族長だ」
「私はシバだ」
そう言って、リザード式のきちんとした礼をとる。クリスは驚いた表情でそれをみつめたあとちょこんとスカートの端をつまむと、お辞儀を返す。
「クリス・ライトフェローです。よろしくお願いします」
その様子が気に入ったのか、デュパはふむふむ、とクリスを観察する。
「よろしくな。鉄頭の子供だが、礼儀はきちんとしつけられているようだな」
「下手したらカラヤの小倅よりもしっかりしてるのかもしれませんな」
「あいつは泣き虫だったからなあ……」
ひとしきり感想を漏らした後、デュパは、自分を見上げる視線にきがついた。
「なんだ」
じーっと見上げているクリスに視線を合わせる。すると、クリスは気遣わしげに言う。
「あの……デュパ様、そんなに大きくお口がさけてて、お口痛くない?」
今度は、シバも一緒になって大笑いを始めた。
「ふ、は、はは、またおもしろいことを考えるな! 痛くないか、とは!」
「え? え? ええ?」
何故笑われているのかわからずクリスはおろおろする。その肩を、アラニスがぽんぽん、と叩いた。
「気に入られたのよ、きっと。大丈夫、リザードのひとたちは見た目ほど怖くないから」
ふーん、とクリスは笑い転げる二人を見る。その顔から、おびえが消えていることを確認して、パーシヴァルはやっと肩から力を抜いた。なんとか、危機は脱したらしい。
「デュパ、あんたなにやってんだ?」
尚も笑っているデュパに、声がかかった。一同が視線を移すとそこにはダッククランの戦士、ジョー軍曹とカラヤのヒューゴがこちらに走ってくるところだった。少々その走り方が慌てているところを見ると、彼らもまた、リザードの面々が何かしはしないかと駆けつけているところだったらしい。
「何も。クリスに挨拶をしているところだ」
「挨拶って……」
近くまでやってきたジョー軍曹はクリスが興味津々といった面持ちで自分を見ていることに気が付いた。こんな見方はゼクセの連中にはよくあることだ。
「あひるさん?」
「そうではありませんよ、クリス様。彼はグラスランドに住むダック族の方です」
「へえー。あのお目目のきれいなお兄ちゃんも、グラスランドの人?」
お目目のきれいなお兄ちゃん、とは青緑の目をしたヒューゴのことだろう。ヒューゴは困った顔で、それでもなんとか笑顔をつくるとクリスに視線をあわせる。
「はじめまして。俺はカラヤクランのヒューゴだ」
「ダッククランのジョルディ軍曹だ。軍曹でいい」
自己紹介をされて、嬉しいらしい。クリスはにこっと笑うとお辞儀を繰り返した。
「初めまして! クリス・ライトフェローです」
「元気な子だな。どこぞの泣き虫とはえらい違いだ」
「私も今そうだと思っていたところだ」
ジョー軍曹の感想に、デュパがうなずく。ヒューゴが真っ赤になった。
「ぐ、軍曹ぉー、デュパ様も……」
「ははは、悪かった悪かった」
皆、ヒューゴをねたに、ひとしきり笑いあう。つと、シバが何かを拾い上げた。
「ん? これは缶か。子供の遊び場にほうっておいたら危ないな」
空の缶を不思議そうに見るシバに、アラニスが言う。
「それは、いいんです。さっきまで缶けりをしてたから」
「缶けり?」
どうやら、グラスランドではあまりやらないあそびらしい。説明すると、グラスランドの人々は、ふうん、となにやら興味を持った様子だ。
「なるほど、隠れるだけでなく、作戦も必要なのだな……」
腕組みをして、頭をめぐらすデュパの服の裾を、クリスがつんつん、と引っ張った。
「ねえねえ、デュパ様も一緒にやろう?」
パーシヴァルとジョー軍曹、保護者二人が声にならない悲鳴をあげる。恐れを知らない子供ほど、怖いものはない。はらはらと周りが見守るなか、デュパはにいっとクリスに笑いかけた。
「よかろう。では私も混ぜてもらおうか」
「デュパ、あんた正気か?」
ジョー軍曹が叫ぶが、デュパは大まじめだ。どうやらシバも加わる気らしい。仲間が増えた、程度にしか思っていない子供騎士団とシャボンがはしゃぐ。
「軍曹はどうする?」
デュパにきかれ、軍曹は肩を落とす。
「……やるよ。なんかもうそっちのお嬢さん的にはメンツにはいってるみたいだし」
あーあ、この歳で子供の遊びか……と、肩を落とす軍曹を、ぽんぽんとヒューゴが叩く。彼は結構楽しそうだ。
「まあ、たまにはいいんじゃない?」
「そうだな……」
「じゃあいくよーっ」
クリスが大声で叫んだ。次いで、かーん、という缶を蹴る小気味よい音が辺りに響き渡った。
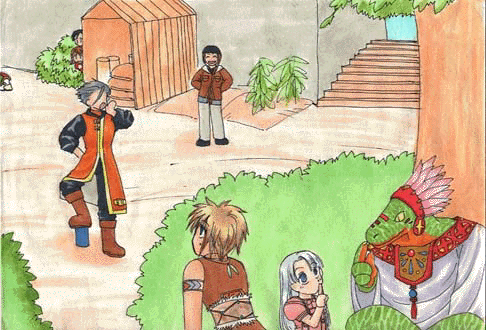
![]()
今回一番かきたかったのは、
しーってやってるクリスとデュパだったり。
ギョームだったり