
「よし、こんなものかな?」
ガナッシュにココアパウダーをふりかけて、クリスが得意そうに言った。
「あら、随分うまくできたじゃないか」
横で見ていたクィーンが、笑う。
「上出来上出来」
エレーンも、ほっと安堵の息を吐いた。
「ありがとう、二人のおかげだ」
顔にココアをつけたまま、銀の乙女はにこっと笑った。
ビュッデヒュッケ城の厨房。バレンタインデーという女性の一大イベントを前日に控え、クリス、クィーン、エレーンの三人は、チョコレートの製作にいそしんでいた。ビュッデヒュッケ城に住む元気な女の子パワーに触発された(毒された?)クリスが、今年、チョコレートを贈る側に回ってみようかと思ったのがそもそもの発端だ。大人の女性に意見を聞いたほうがよかろう、とクィーンに相談したところ、彼女はチョコレートの作り方を教えてくれた。メイミに頼んで厨房を開けてもらい、半日がかりでトリュフを作る。途中、なぜかエレーンも加わり、今に至っていた。
「このガナッシュ、本当においしいのよねえ」
ボウルに残るガナッシュをぺろりとなめ、エレーンが少し悔しそうに言う。三人の作るトリュフに使うガナッシュの、味付けをしたのはクィーンだ。
「ふふ、たまにはシャンパンの香りのするチョコレートもいいだろう?」
「誰かさんの好きな銘柄の酒によくあいそうだことで」
「当然さ」
大人な会話に、クリスは笑みをもらす。鈍いクリスでも、この二人の恋人がそれぞれ誰なのかは知っていた。
「しかし、意外に重労働が多いんだな、お菓子づくりって」
さほどテクニックを必要としない、チョコレート刻みや、生クリームのあわ立てなどを担当させられていたクリスが、こきこきと肩を鳴らした。
「だから女は強いのさ」
クィーンが笑う。チョコレートを刻むついでにまな板を刻んだり、生クリームを泡立てようとして、あっという間に分離させたクリスに不安を感じた二人が、細かい作業を彼女から上手に取り上げたことは、本人には内緒だ。
「さて、あとはラッピングだねえ」
事前に買っておいた、落ち着いた色の包装紙をクィーンが出した。一度テーブルを片付けてそこに広げる。
「ああ、それなんだけど」
エレーンは、何かを思い出したらしく、貯蔵庫から何かを持ってきた。
「これ、クリスにあげるわ」
「何? これ」
それは、ハート型の容器のようだった。茶色いそれは、どうやったのか、チョコレートでできていた。
「すごい! かわいいなあ」
「だろう? 昨日から作っておいたのさ」
エレーンは得意げだ。
「おや、あんたにそんなテクニックがあったなんてね」
「おもしろいだろう? 容器の中に一旦チョコレートを流し込んだ後、すぐにボウルに戻すんだ。すると、残ったチョコレートが、勝手に容器になってくれるって寸法さ。……ただ、あの朴念仁がこれで喜ぶかどうかは疑問だけど」
「カレーを中に流し込んだほうがうけそうだものねえ」
くすくすと二人は笑いあう。
「しかし、そんなに大切なものを私がもらってしまっていいのか?」
不安そうなクリスを見て、エレーンが微笑んだ。
「それの欠点は、型から出すときに割れやすいってことでね。念のため二組作っておいたんだ。けど、今回は一度も割らなかったからね、一組浮いてたんだ」
「ありがとう……ああ、でもどうしよう。これ一つだと、誰か一人ひいきしてしまうな」
チョコレートはきっちり七人分。六騎士とルイス、それから世話になったナッシュのぶんだ。
「おやおや」
からからとクイーンが笑った。
「明日は、誰か一人をひいきする日だろう?」
「ええっ、え、え……」
え、を繰り返しながらクリスがうろたえる。彼女がチョコレートを作りたいなどと言い出した理由はただ女の子達に影響されただけでないことは、二人にはお見通しだ。
「まあ、誰かは聞かないけど? いい機会じゃないか」
本当は、大体見当はついているけれど、という言葉をエレーンは飲み込む。
「いや、それは、そうなんだけど……」
「だけど?」
クィーンに、意地悪く見つめられて。
「わかった……善処、してみる」
ついに銀の乙女は決心をした。
考えてみれば、エレーンの言うとおり、いい機会なのかもしれない。不器用な自分が、誰かに心を伝えるのには、これくらいの小道具は必要だろう。いや、ないときっと決心がつかない。
「じゃあ、先にちゃっちゃとお義理の連中のを片付けるとしますか」
「エレーン、その言いようはどうかと……彼らに感謝の意を表したいとも、ちゃんと思っているのだぞ?」
「二の次、二の次」
「クィーンまで……」
結局、リボンを結ぶこともままならないクリスが包装紙をかなり無駄にして、ラッピングを終了したのはそれから一時間後のことだった。当然、クィーンもエレーンも自分のチョコレートの包装は終わっている。
「すまない。あとひとつだけだから……」
「それは終わってるよ」
「え?」
にっこり。クィーンは笑いながら綺麗に包装された箱をクリスに渡した。
「メイミに約束した終了時間がそろそろだからね。勝手かとはおもったんだけど」
くすくすとエレーンが笑っている。ありがたいやら情けないやらでクリスは肩をおとした。
「まあまあ、落ち込まないの。ほら、これもあげるから」
そう言って、何かをクリスに差し出した。
それは、赤いレース仕立ての造花だった。きつく巻いたバラのつぼみを模しているのだろう。細工がとてもかわいらしい。
「これもそえて渡してあげな」
「え、でも……」
「いいからいいから」
「そうそう。エレーンが何かをあげようなんて、珍しいことをしてるんだからさ、ありがたく受け取っておきなよ」
二人そろって微笑まれて、クリスは顔を輝かせた。
「クィーン、エレーン、ありがとう! 頑張ってみる!」
出来上がったチョコレートを抱えて、元気よく厨房を出て行ったクリスは、そのとき気づかなかった。クィーンとエレーンが珍しく二人協力していたことを。そして、彼女達がクリスの出て行った後、にんまり、と笑いあっていたことを。

突然だが、騎士団一のモテ男、パーシヴァル・フロイライン卿は、不機嫌だった。
今日は年に一度のバレンタイン。ビュッデヒュッケ城の中だけではなく、近隣の村の少女や、はてはゼクセの女性にまで、山ほどチョコレートをもらっているという、誰もがうらやむ状況のくせに、彼は不機嫌だった。
「……」
酒場の片隅。無言で、水割りを喉に流し込む。味もへったくれもなかった。ただ、熱が喉を通り過ぎていく。
「あっれー、パーシヴァルじゃないの。どしたの、こんなところで」
底抜けに明るい声に、パーシヴァルは眉をひそめた。
「ナッシュ殿」
金髪碧眼の若作りナンパ親父、ナッシュである。
「今日みたいな日に、一人で飲んでるなんておじさん意外だな」
「別に、貴方に関係ないでしょう?」
「まあそうだけどね」
それなりに笑い顔を作りながら、この親父につかまるとは俺の運も尽きたかな、と考える。その耳に、ガラスの触れる小さな音が聞こえた。見ると、ナッシュは片手にワインボトル、反対の手にはワイングラスを二個持っている。今酒場で買い求めたものだろう。
全く、この親父でさえ今日共にいる人がいるというのに。
手にもつ品物と、その機嫌のよさに、今日彼になにがあったかを察したパーシヴァルはますます気分が沈んでいくのを感じていた。
「なんか機嫌悪そうだね。こんなにもらっておいて」
ナッシュがパーシヴァルの前のテーブルを指差した。そこには、チョコレートの入った包みが山になっている。
「そこら歩くともらうんですよ」
「うわー、余裕の発言。もらう人は違うね」
「別に、たいしたことはないですよ」
本当、くれた女性には絶対に言えないが、ぶっちゃけた話、こんなものはどうでもいい。このなかに、パーシヴァルの本当に欲しいものはないのだから。
「ふうん?」
にやーり、とナッシュは人の悪い笑顔になった。
この男は、何故人が絶対に気づかないはずのポーカーフェイスを、いとも簡単に見破るのだろう。何か、紋章術の一つではないかと、本気で疑いたくなる。
「で? クリスからはもらえたのかな?」
ただ視線だけで人を殺す術がパーシヴァルにあったとしたら、ナッシュは、即死していただろう。一瞬向けられたその瞳に、ナッシュは「おお怖」と肩をすくめてみせた。
パーシヴァルが不機嫌な理由、それは、自分でも幼稚なことだとは思うが、クリスにチョコレートをもらえなかったということだ。クィーンたちに協力してもらって、チョコレートを作っている。その話は、彼女は知らないだろうが、城内なら誰でも知っていることだ。それで、六騎士やルイスといった面々は、皆一様に期待に胸を膨らませていたのだが。
ルイスは朝一番にもらったそうだ。ボルスは午後クリスの部屋から出てくるときに小躍りしてたから、まあ、もらったことは確実だろう。サロメとレオは、照れながらもらったことを話しあっていた。ロランも珍しく顔をほころばせながらチョコレートを手にしていた。
なのに、何故、自分の手元にはそれがないのか。
今日は仕事の関係で、何回か執務室を訪れていた。だから、機会がなかったわけではないはずだ。
恨まれるようなことをした覚えはない。むしろ、できうる限り、彼女に好意をもってもらえるよう、行動していたはずだ。
彼女の性格上、誰か一人をひいきして冷遇するなどということは、ありえないのだが。
「残念、あれけっこうおいしかったのに」
目は笑ってなくとも、顔は笑っているパーシヴァルを見下ろしながら、ナッシュが言った。その爆弾発言に、ついにポーカーフェイスが崩れる。
「あんたまで?」
口調も崩れた。
それをみて、ナッシュがついに笑い出す。
「くっ。はははははははは、おもしれー」
「わが剣のさびになりたいんですか、貴方は」
ちゃき、とパーシヴァルの鞘が鳴った。
「やめてくれよ、俺はまだ死ねないんだから。そうだな、笑ったお詫びにおじさんが一肌脱いであげるから、それで許してくれない?」
「貴方に脱いでもらってもどうにもなりませんよ!」
「信用ないなあ」
あはは、と笑いながらナッシュはワインボトルを持っているほうの手をパーシヴァルの首に回した。そのまま、強引に相手を立たせる。
「ちょっと、何を……」
「まあまあいいから。とりあえずお前さんは部屋帰んなさいって。あ 、アンヌ、こいつの代金は適当につけといてくれ。このまま連れて行くから」
アンヌは快くそれを引き受ける。二人はもつれ合うようにして廊下へと転がり出た。
「ナッシュ殿!」
「はいはい」
そのまま引きずられるようにして歩く。歳からいえば、そろそろ体力のピークを過ぎているはずのこの男の腕力は、存外強かった。
「先ほどのチョコレートを忘れてきたのですが」
「誰もとらねえよ。明日行けばおいといてくれてる。っていうかそんなもの持ち歩きなさんな」
「そんなものって」
階段のところまで来て、やっとナッシュは腕を離した。
「これからまっすぐ自分の部屋に帰る。オーケイ?」
「はあ」
それが、彼の助言だろうか。わけがわからずパーシヴァルはナッシュを見返す。ナッシュは意味ありげににやりと笑った。
「ま、お前さんもたまには墓穴を掘るってことさ。じゃ、おやすみ。武運を祈ってるよ」
ははは、とまた能天気な笑いを残して、彼は去っていった。
「何が言いたいんだ、あの人は……」
つかみ所がない、と前から警戒をして見てきてはいたが、今回のこれは何だろう。いつもに輪をかけてわからない。
「まあ、いいか」
パーシヴァルは、ナッシュに言われるまま、自室へと向かった。さっきの騒ぎで、もう酒場に行く気はうせている。
部屋の近くまできたところで、クリスに出くわした。
夜も遅いというのに、いまだに騎士服を着ている。まあ、さすがに甲冑は着ていないが。
「パーシヴァル」
「おやクリス様、こんな夜更けにどうされたのですか? 攫われても知りませんよ?」
いつもより、少し揶揄する響きの多いその言葉を、クリスは聞いていなかった。きょろきょろと辺りを見回している。
「お前、一人か?」
「はい」
それが何か、と言う前にクリスは質問を重ねる。
「今暇か?」
「まあ、後は寝るだけですから」
答えると、クリスは大仰にため息をつく。
「そうか、よかった……やっと……」
「やっと?」
「いや! なんでもない! こっちの話だ!! それよりパーシヴァル、ちょっとつきあってくれ」
「いいですよ」
「よし! っと……そうだな、ええと一旦部屋に……いやそうじゃなくて」
ごにょごにょとよく分からない台詞をこねまわしているクリスに、パーシヴァルは当惑する。冗談だろうか? だが、眉間に深い皺を寄せている彼女は大まじめだ。
「クリス様?」
顔を覗き込むと、小さく悲鳴をあげてあとずさる。
「あの……ご用は?」
「え、ええと……とにかくこっちへ来い!」
真っ赤な顔でパーシヴァルの服を引っつかむと、クリスはそのままずんずんと歩いていく。今日はよく引きずられる日である。
クリスの部屋に引っ張り込まれたところで、やっとパーシヴァルは開放された。服の袖の長さが、左右違ってしまっているが、今それについてクリスに抗議したところで、彼女は聞きはしないだろう。
一体、なんだっていうんだ?
今更。
不機嫌に支配されているパーシヴァルは、そんなことを思う。しかし、彼女はそれに気づいていないらしく、また部屋を見回している。
「ルイスは、もう部屋に戻したんだっけ……うん」
がちゃ。
なぜか目の前の女性は、部屋の鍵を閉める。
(それは、普通女性を部屋から出さないために、男がやる行動です)
部屋に、ふたりきり。そんな状況を、何故こうまで力いっぱい作ろうとしなければならないのか。パーシヴァルはいつものくせで、顎に手を当てながら首をかしげる。
説教だろうか。今日、チョコを渡さなかった、そんな罰を自分に与えた理由を説明をするために。
同時に、ちらりとあることが頭を掠めたが、パーシヴァルは気のせいにすることにした。
まさかね。
「ちょっと待ってくれ」
そう言って、クリスは机に向かう。と、かがみこんだ拍子に、ごん、と机に頭をぶつけた。
「クリス様? 大丈夫ですか?!」
駆け寄ると、力いっぱい、彼女は手を振る。
「や、大丈夫だ! たいしたことない! だからその、そこにいろ!」
真っ赤な顔で、半泣きになりながら制される。
この慌てぶり。そして、この赤い顔。
まさかね。
パーシヴァルは先ほど頭を掠めた可能性を、もう一度検討してみる。
「パーシヴァル」
クリスが、何かを持ってこちらに近づいてきた。パーシヴァルは思考を中断する。
「なんでしょう、クリス様」
「その、これは、私の気持ちだ。受け取ってはくれないだろうか?」
そうして、突き出されたそれは、綺麗に包装された箱。一緒に、レース仕立てのバラの花が添えてある。ボルスたちが受け取っていたものとは、明らかに物が違っていた。
え……。
「よいのですか? 私一人だけ違うものを頂いてしまって、誤解、しますよ?」
今の状況が、信じられなくて、口は勝手に天邪鬼な言葉を吐く。クリスは、首筋まで真っ赤になってうつむいた。
「いいんだ、それは、誤解じゃないから」
「誤解じゃない、とは?」
ああ神様、願わくば、今自分の顔がにやけた変な顔ではありませんように。
「そこまで言わせる気か? 鈍い奴だな!!」
怒られてしまった。
その真っ赤な顔が、あまりにかわいくて、とうとうパーシヴァルは笑ってしまった。
「女性に、鈍いと言われたのは初めてですよ」
「からかうな! こっちは真剣にだなあ……」
クリスの言葉は続かなかった。パーシヴァルがその手を取り、恭しく口付けたからだ。
「貴方のお心を勝ち得たことを、心から嬉しく思います」
「……!」
引き寄せて、抱きしめる。かたくなな唇に自分のそれを重ね、ぺろりと舐めると離れた。
「愛して、います。クリス様……」
「パーシヴァル……」
焦点の合わない紫の瞳を見つめ、一層強く抱きしめる。クリスの唇からは、ため息がもれた。
「パーシ……」
彼女の手は、ぎゅ、とパーシヴァルの背中を抱き返してきた。
どれくらい、そうしていただろうか。クリスの苦しそうな声で、パーシヴァルは我に返った。
「パーシヴァル、その、少し苦しいのだが……」
「あ、すいません! 私としたことが!」
慌てて手を離すと、ぱっとクリスは身を翻した。さっき、パーシヴァルにチョコレートを渡したときよりも、更に顔が赤い。パーシヴァルもまた、顔が火照っているのを感じていた。多分、鏡をみれば彼女と同じような顔をしているのだろう。
「大丈夫、ですか?」
「ああ。その……お前の腕の中は暖かくて気持ちいいしな……」
その目はずっと泳いだままだ。パーシヴァルは呼吸を整えると、いつもの調子で笑いかけながら、机に腰掛けた。
「しかし、そうならそうと早く渡してくださればよかったのに。私はてっきりクリス様に嫌われたのだと思って落ち込んでいたんですよ?」
「だってそれはお前が……」
「私が?」
拗ねた仕草で、クリスはパーシヴァルを見る。
「あからさまに包みが他と違うし、恥ずかしいから二人になったときに渡そうと思ってたのに……執務室には大抵サロメやルイスがいるし、お前が外出しているときは、必ずといっていいほど誰か女性が付いて回っているし……」
「すみません」
パーシヴァルは素直に謝った。脳裏に、先ほどのナッシュの台詞がよみがえる。
「これからまっすぐ自分の部屋に帰る。オーケイ?」
なるほど、確かにこれは墓穴だ。自ら彼女を遠ざけておいて、それで勝手に不機嫌になって、また人気の多い酒場にいたのだから。
わびる気持ちと、感謝の気持ちをこめてパーシヴァルはクリスのこめかみにキスをした。
ありがとう。そんなに悩んでくれて。
ありがとう。そんなに好きになってくれて。
微笑むと、クリスはあとずさった。
「いいかげんにしろ、心臓に悪い!」
「嫌ですね」
「パーシヴァル!」
「ああ、そうだ。チョコレート、まだ開けてませんでしたね。食べていいですか?」
「……人の話を聞いていないだろう。食べてくれ」
きっちり返答するところがこの人のおもしろいところだな、と思いながら、パーシヴァルはバラを指にはさむと器用に包装紙を開けた。蓋を開くと、ハート型のチョコレートが鎮座している。
「中にトリュフが入っているんだ。トリュフは……その、ほかの連中と同じだけど」
「そうですか。しかし随分熱烈な台詞ですね?」
「熱烈な台詞?」
心当たりのないクリスは、不思議そうに箱の中を覗き込んだ。チョコレートでできた容器の蓋には、ホワイトチョコレートででかでかと「EAT ME!」と書いてある。
「……クィーンとエレーンのいたずらだな……。そこまで強調しなくても、食べてくれるとは思うが……」
「いえいえ、そうではなくて」
プレゼントを膝の上に載せると、パーシヴァルは片手でクリスの腰を抱いた。
「ん?」
「この言葉には、別の意味もあるんですよ。私を食べて……つまり私を抱いて……ってね」
「!!!!!」
クリスが動作を停止した。あまりのことに、混乱しているのだろう。
「食べていいですか?」
にやりとにっこりの中間で、パーシヴァルは微笑みかける。蛇に睨まれた蛙のように、クリスは身動きできずに体をふるわせる。
「こ、これは、その、あの二人のいたずらで!」
「私達は二人とも健康な成人男女です。そういう関係もアリでしょう。それとも、私ではお嫌ですか?」
「い、いや、嫌だとかそういう問題じゃなくてだなあ!」
「じゃなくて?」
くすくすとパーシヴァルは笑う。
「パーシヴァル……私は……」
「クリス様、このバラの花、とれるみたいですよ?」
急な話題転換に、クリスは相手を睨んだ。
「お前と言う奴は……。花がとれるって何だ?」
「ほら」
パーシヴァルは、造花の花びらの部分をつまむと、額から引き出した。真っ赤なレースが丸まって出てくる。
「一枚布で花びらを作ってたみたいですね」
何か、意味のあるものなのだろうか。レースを広げてみた二人は、今度は同時に動きを止めた。
真っ赤なレース仕立ての花びらは、なんと、真っ赤なレース仕立てのショーツだった。それも、デザインはやらしさ満点の代物で。
「〜〜〜〜〜〜!!!!!」
クリスは恥ずかしすぎて言葉も出ない。おそるおそる伺ってみると、黒髪の恋人は、全開の笑顔で笑っているし。
「やはり、ここまで誘われておいて、何も手出しをしないというのは、相手に失礼というものですよね」
「いや! そんなことはない! っていうか私は知らなかったんだ!」
「ご冗談を」
狼狽しているクリスは、あっさりと壁際に追い詰められる。
「ちょっと待てパーシヴァル! その手はなんだ!」
パーシヴァルは、クリスに手を合わせた。
合掌。
「パーシヴァル!」
「いただきまーす」
ぱくっ。
次の日、クリスは朝部屋から出てこなかったのだが、それが、ただの睡眠不足によるものではなかったそうな。
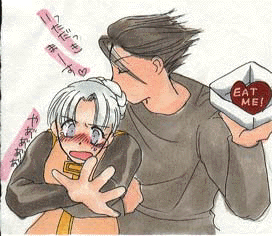

レース仕立てのバラの花は、実際に百円ショップで売られてます
この話では、もっと上品なものというイメージで書いてますが
……結局パンツじゃどうしようもないかな?
>帰ろっと