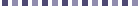
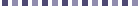
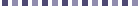
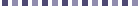
で、俺はいつものようにピンチだった。
鬼上司ササライの命令で、いつものスパイ稼業。とある貴族の館から、あるものをとってこい、というのが命令だ。まあ盗みっていうのは、良心の問題はともかくとして、珍しい命令じゃない。だが、今回はそのあるものっていうのが、かなり厄介な代物だった。
「ナッシュ……」
「しっ……ルネ様。しゃべってはいけません」
俺は抱きかかえている少女に、小さく囁いた。
南の小国のお姫様ルネ、御歳七歳。これがササライ様ご所望の品物だ。この間うちの国に侵略されて、属国として併合されることは免れたものの、人質を差し出すことを余儀なくされたかわいそうな国のお姫様である。
なんで彼女が円の宮殿に収容されるのではなく、俺と一緒にいるのかというと、輸送途中に彼女を攫った馬鹿がいたせいだ。犯人はうちの国の貴族連中。彼女の国をハルモニアに吸収することが出来なかったのが不満だったらしく、人質を『なかったこと』にしてもう一度侵略してしまおうと思ったらしい。
まったく迷惑な話だ。
守銭奴ササライとしてはこれ以上のコストはかけたくないみたいで、その火種をもみ消すべく俺に救出命令をお出しになりやがった。それに俺が逆らうことなどできるわけもなく……こうやってピンチに身を置いている。
俺は、ルネを抱いたまま、辺りを見回した。その先には鬱蒼とした森の闇が広がっている。現在位置は彼女が監禁されていた城から役数百メートル、といったところ。逃亡劇はまあまあ順調と言えるだろう。
俺はなるべく気配を消して、そろそろと移動した。
森は一見静かだ。
だが、その闇の中には、数十人の刺客と、数百に及ぶトラップが潜んでいる。しかも、どの刺客も結構よく訓練されているのが気配でわかった。
(お姫様片手に、たった一人、か。ちょっと荷が重いな)
俺は心の中だけで舌打ちした。
俺一人ならいい。
気配を消すのなんて簡単なことだし、夜目だってきく。刺客を欺いて森を抜けるのなんてたいした仕事じゃない。けれど、今連れているのはまだ小さな子供だ。彼女のおびえる吐息は、どうしたって刺客達の注意を引いてしまう。
「……?」
辺りを真剣にうかがう俺を不安に思ったのか、お姫様が俺を見上げた。
『大丈夫』
目だけでそう言って、笑いかけてやると、俺は彼女の頭をくしゃっとなでた。
これで命惜しさにこの子が見捨てられるなら、俺の人生はもっと楽だったんだけどね。
俺は月明かりを気にしながら、木陰づたいに森を移動する。今日は満月。綺麗な月光も、今日この時だけは俺たちを追い立てる凶暴なあかりと化している。
月光、か。
俺はふとある女を思い出して笑った。
数年前知り合った、不思議な女。
見た目は二十歳にも満たない少女に見えるのに、態度は尊大、口調はオババ。出会ってその日に人を荷物持ちに認定したうえ、その数日後には逃げやがった。必死で探せば、毎回散々に俺を振り回してくれやがる。
そのくせ、月光のように儚くて、綺麗なんだから最高にたちが悪い。
あんたが月の主だっていうんなら、助けてくれよ。
心の中で囁いた時だった。
「……っ?」
妙な気配を感じて、俺は移動をやめた。
かすかな……視線だろうか。
俺の緊張を感じたのか、ルネは身を固くしたまま、息をのむ。泣き出さないだけ、この子供は気丈だ。
闇の中に目をこらす。
そこにあるのは、ただ草陰と、ところどころ差し込む月光だけ。
だけど。
俺は頭の中にたたき込んだ地図と、現在地を測りながら考える。動く……べきか。
ゆっくりと、月光の照らす先に視線を向けたときだった。
「ん?」
そこには、あり得ないものがあった。
「ナッシュ?」
ルネが動揺するのにも構わず、俺は「ありえないもの」に近付く。手にとってみると、それは確かにそこに存在していた。
「……これって……」
俺はそれを手にとるとしげしげと眺めた。
それは、女物のショールだった。ちょうど今日の月光そっくりの、淡い薄紫色の柔らかなショール。顔に近づけてみると、かすかに甘い薔薇の香りがした。
このショールを持っている女を、俺は知っている。
知っている、が、何故これが夜露の一つもつけずにこんなところに落ちているんだ? いや、落ちているというよりは、置いてあったというのに近い形だが。
これは、何なんだ?
俺は辺りを見回した。だがこれ以外に、彼女を思わせるものは何もない。
いや。
俺はある一点で視線を止めた。
ショールを拾った場所から少し離れた木々の間に、不自然に月光が射しているところがあった。
「ナッシュ?」
お姫様は俺を不思議そうに見上げた。俺が苦笑してるからだろう。
「ルネ様これ羽織っていてください。お守りですから」
俺は持っていたショールをお姫様にかけると走り出した。まっすぐに、月光の差し込む場所へと。
まあ、逃亡の常識を考えると、気が狂ったとしか思えない行動だろうな。敵に見つかりやすい月光の中、大事な荷物に目立つショールをつけさせて走ってる。
けれど、賭けてみるだけの価値は、絶対ある。
なにしろあの女の加護だ。
並の女神よりずっと強力に決まってる。
俺は、月光を頼りに走った。
気配を消すこともせず走る俺は相当に目立つはずなのに、追っ手は来ない。時折、遠くからうめき声や雷の落ちる音が聞こえてきたような気がしたが、俺は聞かなかったことにした。
とにかく走るだけ走って、いいかげん体力の限界がつきたときだった。
「……っ!」
森が、切れた。
生い茂る木々の間から外に出ると、そこは丘だったらしい。眼下に小さな集落が見えた。そして、集落の規模には似合わない数の青い軍服の群れ。目を凝らすと、旗に縫い取られた部隊名が読み取れる。ハルモニア軍親衛隊第三大隊……俺の知り合いの部隊だ。
俺は最後の一仕事、と一気に丘を駆け下りた。
「ディオス!」
部隊長の所まで走っていくと、独特の鷲鼻の新米将校がはじかれたように振り向いた。
「ナッシュさん? え? 合流場所はもっと先じゃ……! ルネ様! よくご無事で!」
ディオスは、慌てながらもすぐに駆け寄ってきた。俺は羽織らせていたショールをほどくと、お姫様を地面に降ろす。
「逃げ回っているうちに、ここまで来ちゃってね。かえってかなり近道したみたいだな……」
「かなりどころではないですよ。でもいいタイミングでしたね。あと少し遅かったら、私達も本来の合流場所に移動していたところでしたから」
「そりゃよかった。これ以上走るのは勘弁してもらいたいからな」
俺は大仰にため息をついてみせると、立ったままのルネをディオスに向かって促した。ぎゅ、とルネは俺のマントの端を握りしめる。
「ルネ様。もう大丈夫ですよ。この人は顔は怖いけど、貴女を無事にハルモニアの首都まで送り届けてくれます」
「……はい」
ぎこちなく頷くルネに、ディオスは精一杯笑いかけると(それが余計子供には怖いと思うのだけど)膝を折って頭を下げた。
「このたびは私どもの不手際で怖い思いをさせて仕舞って申し訳ありません。二度とこのようなことがないように、私どもがお守り致します」
「……はい」
「ではルネ様、本日の宿にご案内致しましょうね」
ディオスは立ち上がるとルネの手をとって立ち上がった。なんとかルネは俺の服から手を離す。
「あれ? すぐに円の宮殿に戻らないのか?」
「合流が早くなったおかげで時間の余裕ができましたし、この人数なら下手に夜中に動くより白昼堂々と移動したほうがいいでしょう。まあもっとも、あの貴族連中に、この精鋭部隊に喧嘩を売る度胸があるとは思えませんが」
「そりゃそうだ」
俺は笑った。俺一人ならともかく、ササライに正面か向かってくる奴は今のところいない。
「ナッシュさんはどうするんです?」
「早めに退散……と言いたいところだけど、いい加減疲れたからなあ。どこか開いてる部屋あるか? 一眠りしたいんだけど」
「じゃあそちらの通りにある宿に泊まるといいですよ。うちで貸し切ってますが、部屋はあいているので」
「軍のおごりか。ありがたいね」
俺は空いている部屋の鍵をディオスから受け取ると、しゃがんでルネの額にキスをした。
「ではおやすみなさい、ルネ様」
「はい。おやすみなさい、ナッシュ」
くしゃ、と頭をなでてやると、寂しそうだった少女の顔に、少しだけ笑顔が戻った。
宿の部屋に入ると、先客がいた。
どこからどうやって入り込んできたのか、その先客は、俺が入ってきても驚くこともなくベッドの上に寝ころんでくつろいでいる。
「シエラ」
俺はその肩に口づけると、先客の名前を呼んだ。
彼女は微笑むと、体を起こして俺の首に手を絡ませる。
窓から差し込む月光がそのまま結晶化したような、繊細な美貌の少女。俺はうっとりと見つめると、淡く色づく唇に軽くキスした。
「今日はありがとう。正直、助かった」
「おや、何かしたかえ?」
「とぼけるなよ」
俺は笑うと、さっきからずっと持っていたショールをシエラの肩にかけた。月光色のショールは、まるでシエラのためにだけ存在するかのように、彼女を彩った。
「俺が気づかないとでも?」
「まあそりゃそうじゃの」
くすくすと笑うシエラの腰を、俺は抱いて引き寄せた。
「で? 今回はどういった風の吹き回しで?」
俺は内心、少し警戒しながらそう問いかけた。今日のシエラの手助けは、ありがたい。だが、俺はこの女が下手すりゃ箸の上げ下ろしさえやらないくらいの面倒くさがりだということも知っている。何か裏がないわけないのだ。
吸血の一回や二回ですめばいいんだけど……。
だけど、予想を裏切り、シエラはにっこりと優しく笑った。
「別に他意はない。今日のはおんしへのプレゼントじゃ」
「プレゼント?」
俺は、きょとんとしてシエラの瞳を覗き込んだ。珍しく穏やかなルビーアイには嘘はないようだが。
「本当に……? 本気でなんにも裏はないわけ?」
「ないと言っておろうが。なんじゃ、あって欲しいのかえ?」
じろり、と睨み付けられて俺はあっさり謝った。
「いいえ、ないのが一番です」
「わかればよいのじゃ」
尊大に言い放つと、シエラは俺の胸に顔を埋めた。首筋を狙ってくる気配はない。どうやら本当に血がほしいわけでも、俺に何かさせようとしているわけでもないらしい。不思議に思って首を傾げていると、シエラがとうとう吹き出した。
「なっ、何だよ!」
「いや……本当におんしはアホじゃと思うて」
「あほって……」
シエラは、顔を上げると俺の顔を両手で挟んだ。
「おんし、今日が何の日か思い出してみるがよい」
「今日? え……? 何かあったっけ? ……えーとクリスマスはもっと先だし、正月は更に先だし、バレンタインはもっと先だし……エイプリルフール……でもないよなあ。あとは……」
「おんしは本当に自分のことに関しては無頓着じゃのう」
「自分? え……自分って……あ。そうか! 俺の誕生日か! 今日は!」
「やっと思い出したかえ?」
笑われて、俺はやっと思い出した。そうだ、今日は俺の誕生日だった。そういえば、前にシエラの誕生日を祝ったときに、お返しは何がいいかと問われた気がする。
「覚えててくれたんだ……ありがとう」
普段不幸体質な反動か、それとも女王様すぎる彼女の性格のせいか、ものすごく、ものすごく心から嬉しい。
「まあ、礼を欠かせては女がすたるからのう。今日も生き延びておめでとう、ナッシュ」
「ありがとう。あんたのおかげだよ」
今日は特に。
言うと、シエラはまた笑った。
「プレゼントは気に入ったかえ?」
「うん。……あ、でも」
「ん?」
「もうちょっとだけ、欲しいかなー、なんて」
俺はもぞもぞ、とシエラの腰に回していた手を移動させた。シエラが、その手の意図に気づいて身をよじる。
「こら! ナッシュ!」
「俺はこっちも欲しい。ダメ?」
「だ……っん!」
シエラの返答を待たずに、俺はその口をキスで塞いだ。
翌日。
昨夜の労働&運動(余計なものも含む)のせいで、鉛のように重い体を引きずり、お姫様の見送りに出てきた俺は、いきなり睨まれた。
「え……?」
昨日、命がけで救出したおかげか、かなりなついて来てくれていたはずの彼女が、何故か俺をものすごい勢いで睨んでいる。
何故だ。
……俺、そんなに子供に嫌われるようなタイプじゃなかったと……思うんだけど。
「あの……ルネ様?」
手を伸ばしたら、ぱしん! と叩かれた。しかも、お姫様は全速力でディオスの後ろに隠れて一言叫ぶ。
「ナッシュのえっち!」
「えっち……何ぃ?」
俺は呆然として固まった。まわりではひそひそと兵達がなにかよからぬことを言い合っている。
ちょっと待てー! いくら俺でも七歳児に変なことはしないぞ!
「ナッシュさん」
混乱する俺の肩を叩いたのはディオスだった。
「ディオス……これは一体何なんだ」
「私もあまり人の生活に口を出すつもりはないのですが……その、任務が終わったとたん部屋に女性を連れ込むのはどうかと……しかもまだ年端もいかぬ少女を」
ぴき。
俺は顔を引きつらせた。
アレか? 昨日のシエラとのアレか?
「ちょっと待て、なんでそれをルネ様が知ってるんだ」
「昨日……不安で寝付けなかったようで、夜中にナッシュに会いたいと部屋を抜け出されまして」
「抜け出させるなよっ!」
悲鳴じみた声で、抗議するが、ディオスもあまり同情はしてないだけあって、対応はそっけなかった。お姫様に視線を戻すと、あっかんべー、とされているところだった。
確かに女は連れ込んだけどさ。しかもやましいこともしてたけどさ。でもって女の見た目は少女にしか見えないけどさ。その上詳しい事情なんて話せないけどさ。
「……」
俺は泣きたくなった。
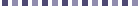
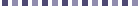
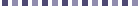
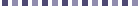
2004年冬コミ新刊原稿です。
満月の加護、というかシエラ様の御利益をテーマにした一冊でした。
シエラ様の加護は確かに効果抜群……ですが、
それと同時に災厄もてんこもりで提供してくださいます。
戻ります