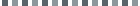
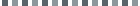
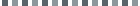
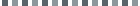
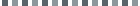
※ご注意※
こちらの作品は、16年前を舞台にフェリドとアルシュタートの出会いをテーマにした、大捏造話です。
大体は古い本、ワールドマップ構成を元に作成していますが、捏造、妄想設定が多々存在します。
捏造&妄想は腐女子の醍醐味、と笑いとばしてお楽しみください。
あ、あとめっちゃくちゃ長いんでがんばってください。
鵬翼の空
「お逃げなさい!」
それが、少女の発した第一声だった。
「は?」
少女の発言が理解できず、フェリドは少女を見下ろす。少女は背中に小さな女の子をかばいながらフェリドをにらみ返した。
「逃げろって……あんたなあ」
「ここは危険です。今なら追っ手も貴方の存在に気づかないでしょう。今すぐに見たことを忘れてこの場から逃げなさい!」
少女はもう一度フェリドを怒鳴りつけた。
「……はあ」
「はあじゃありません!」
奇妙な少女だった。
銀をそのまま紡いだような銀髪に、極上のサファイヤよりも深い色の瞳。幼いながらも気品と威厳を備えたその美貌は、怒りによってばら色に染められた表情であってさえも美しい。
どこかの高位の貴族の娘なのだろう、質のよい絹の着物と労働とは無縁の白皙の肌から、それが見て取れた。
誰からも愛されて、ぬくぬくと守られているはずの立場の少女。
だが、今彼女は闇夜の深い森の中、小さな女の子を背にかばいながら、死体に囲まれてしゃがみこんでいる。
妹だろうか?
かばわれている十にも満たない女の子は、少女とそっくり同じ色の髪と瞳をしていた。
「なあ、今殺されかかってたの、あんただよなあ」
周りに散らばる死体の半分を製造してしまったフェリドは、しゃがんで少女と目線を合わせた。
「で、それを助けたの、俺だよなあ?」
「それが危険だというのです」
「…………一番危ないの、あんただろ?」
そう言うと、少女はぐっと言葉に詰まった。
フェリドがロードレイクの森にやってきたのは偶然だった。
弟の視察につきあってファレナの外洋港エストライズに来て、竜馬の噂を聞き込んだのがきっかけだ。水陸を縦横に駆ける竜のごとき馬はファレナにしか生息していない。どうしても見てみたくなって、仕事を手伝えと文句を言う弟を言いくるめて旅を決め込んだのが十日前。途中、至宝とさえ言われるロードレイクの緑も見たくなって、寄り道して森に迷い込み、街に戻るのも面倒だったのでのんびり野宿をしていたのだ。
その夜中、悲鳴が聞こえた。
獣のものではない、人間の、それも女の悲鳴。
森がなにやら騒がしくなっていたことに気づいていたフェリドは、すぐにその場から駆けだした。
見知らぬ森を、勘ととぎすまされた感覚だけを頼りに駆け抜ける。
悲鳴の元にたどり着いたフェリドが見たのは、ちょうど少女を守っていた護衛の最後の一人が切り倒される場面だった。
すぐさまフェリドが彼らの間に入り、ただの暴漢というには強すぎる男達を切り捨て見事少女達を守り抜いた……のだが。少女に手をさしのべたら、いきなり叱りつけられたのだ。
「彼らを倒して下さったことにはお礼を申し上げます。ですが、妾達に関わってはなりません。でなければ、貴方まで命を狙われてしまいます。早く、この場を」
少女は、頑ななまでにフェリドの助けを拒否し、身を案じる。フェリドは呆れてため息をついた。
「確かに、ここにいつまでもいたら危険だろうな。あんたを襲っていたのは組織的な暗殺者だ。こいつらが戻ってこなければ、また新たな暗殺者が派遣されるんだろう。さっさと逃げたほうがいい」
「では……」
「だが、逃げるのはあんたと一緒だ」
「きゃあっ! 何をするのです!!」
「あ、姉上ぇ、姉上ぇ!!」
フェリドは少女を片手で軽々と担ぎ上げた。そしてあいている手で女の子を脇にかかえる。
「ぶ、無礼な……!! お、おお降ろしなさい!」
「騒ぐなって。暗殺者に聞こえるぞ。どうせさっきの殺し合いのせいで腰が抜けて立てないんだろ? 俺が運んでやるから捕まってろ」
「妾と一緒では貴方が危険に……!」
「そう言われて見捨てられる性分なら、そもそも助けに入らないって」
フェリドは、少女と女の子に笑いかけると、疾風の速さで森を駆け抜けた。
「あ! 姉上! お兄ちゃん帰ってきたよ!!」
翌朝。
森の外れの洞窟へと馬を連れてやってきたフェリドは、小さな女の子の歓迎をうけた。
「おー、無事だったな?」
「お兄ちゃんもお帰りなさい!」
陽光をはじく銀の髪にサファイアの瞳。昨日助けた少女二人のうちの、幼いほうの少女だ。彼女は、襲われていた昨日とはうってかわって元気いっぱいにフェリドに抱きついてくる。フェリドは笑いながら女の子を抱き上げた。
「お待ちなさい。周りの安全を確認せずに飛び出してはいけませんよ!」
女の子にやや遅れて、もう一人少女が出てきた。こちらも、髪は銀で瞳は蒼。昨日フェリドを叱りつけたあの少女だ。彼女の気の強さは、昨日と変わらない。
「ごめんなさい……姉上」
「まあまあそう怒るな。こいつだって不安だったんだ」
「それは……そうですけど」
「何にせよ無事で良かった。服と飯と馬、調達してきたぞ。腹減っただろう、甘いものも買ってきたぞ?」
「わあい! お兄ちゃんありがとう!」
フェリドは洞窟の中に入ると、明かりをともして荷物から食事を取りだした。甘い菓子パンを渡してやると、女の子は嬉しそうに受け取る。
「いただきまーす」
「おう。あんたも一つどうだ?」
「いただきます」
少女は、フェリドから食事を受け取ると上品に食べ始めた。
「ロードレイクへの往復にしては、時間がかかったようですが、何かありましたか?」
「ああ。ロードレイクは今騒ぎが起きていて、入れる状態じゃなかったからな。レルカーまで行って買ってきた」
「ありがとうございます。……街の様子は、どうでした?」
「なんでもロードレイクの南にある女王家の別荘が焼かれて女王の孫娘二人が殺されたとかで、大騒ぎだったぞ。レルカーもすぐ隣の街だから、だいぶぴりぴりしていた」
報告してやると、少女は小さく息を呑んだ。悔しそうに目を伏せる。
「飯を食ったら、あんたを好きな所まで送っていってやるよ。……と、そういやばたばたしていて名前も聞いてなかったな。俺はフェリド、あんたは?」
フェリドが尋ねると、少女はまた息を呑んで口をつぐんだ。大体少女が何故黙ったのかわかっているフェリドは深々とため息をつく。
「あんたの名前を聞いたら、ますます深みにはまるとか言わないでくれよ? もう既に俺は深みにはまってるし、あんたを安全な所まで送り届けるまでは手を引くつもりはないんだ」
少女は、申し訳なさそうに目を伏せた。
「申し訳ありません……そうですね。もう、貴方は立派な関係者でしたね。妾の名前は、アルシュタート=ファレナス。この子の名前は……」
「サイアリーズ=ファレナス! よろしくね、お兄ちゃん」
「アルシュタートにサイアリーズ、か。なあ、それって昨日の夜ロードレイクで殺されたっていう御姫さん二人の名前なんだが、どういうことなのか教えてくれないか?」
なんとなく予想していた答えを聞いて、フェリドは笑った。アルシュタートの表情は益々曇る。
「恐らく、昨日妾達を襲った者どもの仕業でしょう。別荘で妾達を殺し損なったため、代わりに誰か年格好の似ている者に妾達の服と装飾品を着せて殺したことにしたのです」
「別荘が焼かれたのは、死体を焼いて区別をつきづらくするためか……」
「ええ。妾達を表向き死んだことにして、孤立したところでゆっくり殺すつもりなのでしょう」
アルシュタートは深々と息を吐いた。
「身代わりにされた者は、年端もいかぬ子供だったでしょうに……むごいことを」
「あんた、黒幕に目星はついているのか?」
「誰、と特定はできませんが、大体の見当はついています。ファレナの2大貴族のうちの一つ、ゴドウィン家の誰かでしょう」
「恨みでも買ってるのか?」
フェリドが問うと、アルシュタートは首を振った。
「政敵とされています」
「そりゃあ恨みよりたちが悪いな……」
「今、女王家には次期女王候補が二人います。姉姫であるシャスレワール様と、妹姫である我が母ファルズラーム様。シャスレワール様にはゴドウィン家の者が、ファルズラーム様にはバロウズ家の者が婿として入っています」
「なるほど、女王候補の対立がそのまま貴族の対立になってるってことか」
「ええ。現在の女王様であるオルハゼータ様の夫はゴドウィン家の方。政治的に不利と感じているバロウズ家の者達の活動が最近活発になっていたせいでしょう。危機を感じたゴドウィンの者達が……」
「次期女王候補の跡継ぎを殺そうとした……そうなんだな?」
「はい」
アルシュタートはこっくりと頷いた。
「ファレナのしきたりでは、葬儀と同時に戸籍が抹消されます。そうなれば、たとえ生きていても王家に戻ることはできません。なんとしても、生きてソルファレナに戻らなくては」
「ねえ姉上、どうやって帰るの? お迎えが来るの?」
「サイアリーズ、私たちは死んでしまったことにされているの。だから、お迎えは来ないの」
「でも心配することはないさ」
不安そうになったサイアリーズと、表情の硬いアルシュタートの背を、フェリドはばんばんと叩いた。
「俺が安全なところまで送ってやるよ」
「……危険ですよ」
「望むところだ」
フェリドがにやっと笑うと、アルシュタートは苦笑した。
そしてそのまた翌日。レルカー近くの川のほとりで農作業をしていたオヤジは、奇妙な三人連れに声をかけられた。
馬を引く武人らしい威丈夫と、その馬に乗る小柄な少女と小さな女の子。少女達二人は日よけのためかマントの上からすっぽりとフードをかぶっていて顔が見えない。そのうちの威丈夫がオヤジに向けて手を振っている。
「おーい、ラフトフリートってのは、この先にいるのかー?」
「ラフトフリート? ああ、あいつらか。そうだなあ、3日前から上流に来てたなあ。ほれ、あっちに見える竜の形したでっかい船が頭領の船だよ」
「へえ……本当に川の上で生活してるんだなあ……」
男が感心するようにそうつぶやく。オヤジはそれを見て笑った。
「なんだ、ラフトフリートを知らないなんてお前さんファレナの民じゃないね?」
「ああそうだ。群島諸国から来たんだ」
「へえー、移住かい?」
彼らの馬の鞍には大きめの荷物がくくりつけられている。しかし男は首を振った。
「いや、旅行だ。所謂新婚旅行ってやつでね。カミさんと、その妹と一緒に物見遊山さ」
男は嬉しそうに馬上の少女の手を引いた。
妻と呼ばれた少女の服の間から除く手足は男と同じに小麦色をしている。群島諸国は日差しの強い国だ。自然と肌の色がそんな色になるのだろう。
「新婚旅行に、妹連れ?」
「どっちも他に身よりがなくてな、置いていけなかったんだ」
「……お兄ちゃんは、サ……じゃなかったベルナデットがいちゃ邪魔?」
馬上の女の子が、しょんぼりとしながら言う。
「そんなことはないぞーベルナデット! かわいい妹を俺が置いていけるわけないじゃないか。なあ」
ぐりぐり、と男が女の子の頭をなでると、女の子は嬉しそうに笑った。
「あーなんだ、そういう理由かいな。えらく変な連れだから、どういう関係かとおもっちまったよ」
農家のオヤジはあはは、と笑う。
「しかもヨメさんはえらい若いしよぉ」
「わかってないなああんた」
不思議がるオヤジに男がにやりと笑った。
「女ってーのは、これくらいっから手取り足取り育てるのが醍醐味ってもんじゃねーか」
「……好きもんだねえ、あんたも」
「まだ胸もケツも足りねぇがそこは揉んででかく……」
「旦那様、も、もうご冗談はそれくらいに……!」
さすがに恥ずかしくなったのか、少女が男を止めに入った。おおすまん、と男が顔をあげる。
「わかったわかった。悪かったよフレア、冗談はこれくらいにしておいて先を急ぐことにするから。じゃあな、ありがとよ、オヤジ!」
男は、朗らかに笑うと馬を引いてその場を去っていった。
そしてしばらくしてオヤジの目がなくなったころ、男……フェリドはアルシュタートに怒鳴られていた。
肌の色を隠すために色粉を塗っている顔が、羞恥で更に赤くなっている。
「……っ、ふ、夫婦という設定はともかくっ!! そなたという人は何故あんな下品な物言いばかりするのですかっ!!」
「しょうがないだろ? 見た目つりあいとれないのは事実なんだし。言い訳するしかないだろ」
「だからって……あのような……」
「ねーねー、お兄ちゃん、胸って揉むと大きくなるのー?」
二人の言い争いも気にせず、サイアリーズは無邪気に訊いている。フェリドは豪快に笑った。
「なるけど、サイアリーズにはまだ早いからなあ。将来できた恋人にでも揉んでもらえ」
「あたしじゃなくて、姉上の胸だよー。全然おっきくならないんだもん」
「ああ確かに」
「フェリド! 妹に変なことを吹き込まないでください! サイアリーズ!! そなたも一緒になって変なことを言うのではありません!」
一際高い声でアルシュタートが怒鳴る。フェリドはまじまじとアルシュタートを見た。
「なんだ、気にしているのか?」
「気にしてません! そんなことで女の価値は決まりません!!」
「でも子供育てる時とかさー」
「フェリド!!」
数刻後、フェリドはラフトフリートの漁師に、またもや不思議そうな表情で見られていた。
今度は、旅の取り合わせが不思議に思われているのではない。フェリド自身が不思議に思われているのだ。
「あんた、顔どうなさったね」
「ちょっとした夫婦喧嘩だ。気にするな」
「気にするな……ったってなあ……まあえらいくっきり手形がついたもんじゃ」
「うちの嫁さんは、意外に力持ちなんだよ」
フェリドはこっそり目だけで馬上のアルシュタートを見やった。フェリドの頬に綺麗な手形をつけた犯人は、じっと黙ってフェリドを睨み付けている。
(冗談のつもりだったんだがなあ……)
フェリドは苦笑ひとつしてから、漁師に向き直る。
「ラフトフリートの頭領に会いたいんだ。会えるかな?」
「ラージャ殿にかい?」
「群島諸国経由で商売の話をね。ほら、群島諸国連合艦隊の隊章」
フェリドは懐から小さな指輪を出して漁師に見せる。漁師は頷くと、奥の巨大な船を指さした。
「頭領なら、ダハーカ……あの一番でかい船の最上階にいるよ。馬はここに置いておきな。急に船に乗せると怯える」
「わかった」
少女二人を馬から下ろすと、フェリドは荷物を持ってダハーカに向かった。双頭の竜の形をした壮大な船は見る者を圧倒させる。
「……群島諸国にも巨大な船は多いが、この船はまた独特だなあ」
「ラフトフリートの旗印のようなものですからね。このデザインはシンボルの要素が大きいのでしょう」
アルシュタートが囁く。
「あー、確かに群島諸国も艦隊の旗艦はかなり派手ででかいな」
「このお船より大きいの?」
「リノ=エン=クルデスっていってな。五階建ての巨大船だ。昔昔に群島諸国の連合艦隊ができたころ、旗艦にオベル王国の民が丸ごと乗って夜逃げしたことがあったらしくて、それ以来むやみやたらにでかいのを作るのが伝統になったんだそうだ」
「お船に国の人が全部乗ったの? すごーい……」
「といってもオベルは小さい国だからなー。たいしたことないって。だいたい、でかい船って小回りきかないんだよなあ」
フェリドは苦笑した。
「だからこその旗艦なのでしょう。ラフトフリートも、ダハーカ以外は小型船がほとんどです」
「通商船っていうよりは家だな、この船達は……」
「ここは川に住まう者達の集まりですからね。文字通り船が家で終の棲家なのですよ」
「だからこその自治権……そして貴族からの自由度の高さ、ということか」
「そうです」
首都ソルファレナに戻るためにアルシュタートが目指した場所、それがラフトフリートだった。
ロードレイクからソルファレナへは遠い。船を使わなければ、ニセの遺体を運ぶ船を追い越して、葬儀までに帰り着くことは出来ない。しかし、それは敵も考えていることでもある。主要な港や船着き場は既にゴドウィン派の貴族の手によて押さえられていた。
だが、自治権をもち、貴族権力とは無縁に生きる船乗りと漁師のあつまりラフトフリートなら別だ。監視の目をくぐり抜けて自由に船を出すことが可能である。
アルシュタートはダハーカにのぼる階段を上がった。間にサイアリーズを挟んでフェリドが続く。
船に乗り込むと、外から見ていた以上に壮麗な装飾が目に飛び込んできた。
「中まで派手なんだな」
「この辺りはラージャ様の趣味だと思いますわ。確か……この上でしたわね」
アルシュタートの先導に従って、三人はどんどん上に上がる。三階にあがったところで、派手な屏風を背にした老婆が三人を出迎えた。
「ラージャ様、お久しぶりです」
「ん? 誰だい?」
老婆は顔に皺を寄せて笑いかける。ずいぶんと風格のある老婆だった。痩せてはいるが、頼りなさはない。鉄火肌の姉御がそのまま年を取って頭領になった、そんな感じだ。
「妾です、アルシュタートです。こちらは妹のサイアリーズです」
アルシュタートは頭からかぶっていたフードをとってラージャの前でお辞儀した。同時に手ぬぐいで顔の色粉を少し取る。
「おお……アルシュタート姫様……!! なんだい、ロードレイクで死んだときいていたんだけど生きていたんだね……!! そうかい、こっちがサイアリーズ姫様かい。小さいのによく無事で……!!」
ラージャは立ち上がるとアルシュタートとサイアリーズを交互に抱きしめた。損得ぬきに彼女たちの安否を心配していた人物が現れたことにフェリドはほっと息をつく。
「ラージャ様……」
「貴族連中がいがみ合うのは勝手だが、女子供が死ぬのは嫌だからねえ。無事でよかったよ。それでなにかい? そこのでっかいのがあんたたちを助けた用心棒ってとこかい?」
でっかいの呼ばわりされたフェリドは苦笑する。
「そうだ。名はフェリドという。よろしく」
「ふーん、口のききかたはなっちゃいないがいい目をしてるじゃないか。いい奴に助けられたね、アルシュタート姫」
「え、ええまあ……」
苦笑いするアルシュタート達を座らせると、ラージャは自分も座った。
「で? 私の所に来たってことは、ソルファレナに送ってほしいってことかい?」
「そうです」
「ふむ……あんたたちを送るなら、ただ街に連れて行くだけじゃなく女王の前にまで引っ張って行かなきゃならないねえ。それに時間も考えなくちゃならない。確か王族は葬儀で戸籍が消されるんだろ?」
ラージャは、懐から地図を取り出すとアルシュタート達の前に広げた。
「ここが今ラフトフリートがいるところ。で、こっちがあんた達の遺体を運ぶ船がいるところだ」
ラージャの指した場所は、遺体を運ぶ船のほうが首都に近い。人目をさけて馬で移動したせいだからしょうがないとはいえ、アルシュタートの顔がまたこわばった。それをみてラージャがかかか、と笑う
「まあ今どっちが首都に近いはは関係ない。要は葬儀が行われるまでの時間さね。船がソルファレナにつくまでがあと二日。それから葬儀が行われるまでに一日……ということで三日後の昼前がぎりぎりってとこか」
「行けるか?」
フェリドの問いにラージャは首をかしげる。
「難しいねえ。ただソルファレナにつくだけなら、うちの快速船で一日だ。だけど、ゴドウィンの暗殺者の目をかいくぐって街の中に入るにはちょいと工夫がいるよ。ただその工夫をするだけの時間がねえ……」
「アルシュタート、これだけ大きな街だ。どこかに王族だけの抜け道とかはないのか?」
「いくつかは知っていますけど……使えそうなものといえば、街から王宮に続く道くらいでしょうか」
アルシュタートはすい、と街の一点を指さした。
「なんだ、もっとありそうなのに」
「本当はあるのでしょうけど、それは王族の中でも女王自身にしか教えられないものなのです。特に今は母上と叔母上で対立していますから……」
「下手にどちらにも教えられないってことか」
「はい」
「まあ、ないもんはしょうがないさ。町中まで入ることができればそこから抜け道があるんだろ? だったら町中に入るための道をこっちから作ろう。それくらいなら間に合うだろうよ」
ラージャは地図の上の山の中に指で線を引く。
「抜け穴? 今からですか?」
「ああ。一人……いや一組か、いい逃がし屋がいるんだ。あいつらなら二日で抜け道を作るだろう」
「船で一日、抜け道を造るので二日、か。ぎりぎりだな」
「急ごしらえの作戦なんだ。贅沢をお言いでないよ。ああそうそう、もう一つ問題があった。アルシュタート姫様、ところでお代はいくらもらえるんだい?」
ちろり、と目線を送られてアルシュタートが慌てた。
「お、お、お代……ですか?!」
「そうだよ。私ゃゴドウィンともバロウズとも中立の立場のラフトフリートさ。何の見返りもなく手を貸しちゃあバロウズ家に味方したと思われかねないからね。情とは別に、相応の代価を頂くよ」
「そ……それ……は、戻ってから……ではだめですか?」
暗殺者に狙われて、着の身着のままで出てきたのだ。彼女達は当然金目のものなんて持っていない。今着ているものや馬も、出世払いの約束でフェリドが調達してきたものだ。
「あんたが途中で死んだら回収できないからねえ」
「う……」
「おいあんた、こいつらが金目のものを持ってないってこと、わかってて言ってないか?」
フェリドが不機嫌に口を挟むと、ラージャはにやりと意地悪く笑った。
「持ってるじゃないか。ほら用心棒、今あんたが脇に抱えているものだよ」
「脇? って、ああこの包みか」
フェリドは言われて、荷物を広げた。この中には、アルシュタートが昨夜まで来ていた衣装が入っていた。捨てても売っても足がつきそうだったので今の今まで持っていたのだ。
「見せてごらん」
ラージャは衣装を手に取った。
「ふむ……これはまた上等の絹だね。つくりもいいし、染めもいい。こっちの装飾品は翡翠かねえ。これもかなり上等の品だ。うん、これなら十分対価になるよ」
「ら、ラージャ様、でもそれは」
アルシュタートの声がうわづる。その衣装は、襲われていたときに着ていたもの。服の端には血がついているし、泥で汚れてとても商売になるものではない」
「なんだい、この私の目利きを疑うのかい?」
有無を言わさない勢いで訪ねられて、フェリドとアルシュタートはようやくラージャの意図を理解した。
彼女は最初から助けてくれるつもりだったのだ。
だが、そうするには、貴族達への対面を整える必要がある。金を支払われたから働いたという対面のため、形ばかりの対価として、アルシュタート達の衣装が必要なのだ。
「ありがとうございます、ラージャ様。このご恩は決して忘れません」
「姉上、どういうこと? あたしたちの服があれば、お船に乗せてもらえるの?」
「大人には、いろいろと人の目を気にしないといけないことが多いってこと。大丈夫ですよ、サイアリーズ。ちゃんとソルファレナに戻れますから」
アルシュタートが笑いかけると、サイアリーズは納得したようだ。やれやれ、とラージャが立ち上がる。
「さてと、じゃあすぐに手配をしようかね。キサラ! キサラはいるかい?」
「はい、頭領。こちらに」
ラージャが声をかけると、階下から少女が一人現れた。アルシュタートより二つ三つ上だろうか。漁師らしいはっぴにスパッツ姿が凛々しい美少女である。少し発育が良すぎるのか、胸のサラシがきつそうだ。
「この三人をソルファレナまで送ってやってくれ。途中のバスカ鉱山に逃がし屋のログってのがいるから、そいつにソルファレナの下水道まで道を造れって言ってくれ」
「わかりました」
キサラはラージャから金を預かるとフェリド達に向き直った。
「ずいぶん若い船乗りだな?」
フェリドが言うと、ラージャは笑い出した。
「女を見た目で判断するもんじゃないよ。このキサラはうちで一番の船乗りさ。この子以外に期日までにソルファレナに送り届けることのできる奴はおらんよ」
「これは……失礼した」
「わかればいいんだよ」
「キサラさん、よろしくお願いします」
「よろしくお願いします!」
アルシュタートとサイアリーズが丁寧にお辞儀する。その態度の違いにフェリドが思わずぼやく。
「……俺のときは逃げろだのなんだの言ったくせに……」
「そ、それはそなたの現れ方が悪かったせいです! その後だって口は悪いし下品なことは言うし……」
「なんだ、まだ根にもってるのか?」
本当に揉んでやろうかと言うと、再度平手打ちが襲ってきた。
緩やかに流れるフェイタス河の水面に歌声が流れる。
低く、柔らかに紡がれるメロディはひどくやさしく、水音の旋律と驚くほどとけあう。
「いい声だな」
フェリドは船の操舵をするキサラに声をかけた。
流れの紋章を取り付けた快速船をあやつるキサラは、一瞬だけ振り返ってからまた操舵に戻る。紋章の力で速度を出しているこの船の操作には気を遣うのだ。
フェリド達一行は、キサラの船に乗せられてフェイタス川を北上していた。船で半日ほどの距離にある逃がし屋のねぐらに行くためだ。
「ただの子守歌さ」
「河の音によくあう。将来あんたに子守歌を歌ってもらえる子供は幸せだな」
「早めに歌ってやりたいところだけどね、まだ相手がいないんじゃ宝のもちぐされさ」
あんた、口説いてるのかい?
そう聞かれてフェリドは笑い出した。
「まさか」
「だろうねえ。どこかにいないかな、命がけで私を守ってくれる人」
「なかなかいないだろうそういう奴は」
「姫様にはもういるみたいで、私はうらやましいわ」
くすくす、とキサラは笑う。
二人して笑っていると、フードをかぶったサイアリーズが船の中から出てきた。
「どうした、サイアリーズ」
ラフトフリートの船は、屋形船のような造りになっていて、船の中央部は居住区になっている。せっかく寝床も時間もあるのだから、昨日寝てない姫達二人には眠っていてもらおうと思っていたのだが。
「ねてなくちゃだめだろう?」
「あたしは、お兄ちゃんがお買い物に行っていたときに寝てたからいいの。それより姉上をゆっくり寝かせてあげたいもの」
「そうか。サイアリーズはいいこだな」
フェリドが笑いかけると、サイアリーズはちょこちょこと歩いてきてフェリドの横に座った。
「ねえねえお兄ちゃん、お兄ちゃんは強いよね?」
唐突な問いに、フェリドはきょとんとした。
「ん? そうだな」
「じゃあさ、トウシンサイに出ても、きっと優勝できるよね!」
「トウシンサイ? なんだそれは」
不思議そうなフェリドに、キサラが答える。
「ファレナの伝統的な闘技大会さ。そろそろ行われるんじゃないかって噂はあったんだけどねえ」
「外国人でも参加できるのか?」
「今敵対してるアーメス国の人間だったら無理だけど、それ以外の国なら参加は許可されてるよ」
「あのね、あのね、あたし、お兄ちゃんに闘神祭に出て欲しいの。それから優勝してくれるととっても嬉しいの!!」
最初は興味なく聞いていたフェリドも、サイアリーズの勢いに押されて後ずさる。
「優勝って、お前なあ」
「ねえお願い!」
「……わかったわかった! この騒ぎが終わって余裕があったら出る。それでいいか?」
「絶対優勝してね!」
「私もあんたが優勝したら嬉しいよ」
「……優勝優勝って……何かおもしろいことでもあるのか?」
「それはねえ……」
サイアリーズがいらずらっぽく笑いながらそれに答えようとした時だった。
キサラが珍しくフェリド達を振り返った。
「残念ですが、会話の時間は終わりのようです。サイアリーズ様、アルシュタート様を起こしてください。もうすぐバスカ鉱山です」
「はーい」
サイアリーズはぴょこんと立ち上がると、奥に入っていった。フェリドが体を起こすと、水面の先に黒々とした岩盤で固められた岸壁が見える。
「あれか?バスカ鉱山っていうのは」
「そうだよ。あそこに逃がし屋がいるって話だけど……」
逃がし屋がいるかどうかは、すぐにわかった。
岸に上がると同時に出迎えが出てきたからだ。……それもものすごく騒がしい出迎えが。
「おっほー! こりゃまた別嬪のお客ばっかりだなあ!」
「お客、別に別嬪でもどっちでもいい。金払ってくれたらそれでいい」
「なんでえガン公おめえもつまんねえ奴だな」
「俺、つまんなくていい」
鉱山の洞窟から出てきたのはなんとも珍妙な二人組だった。
一人は体が縦にも横にも大きな無精ひげの男。もう一人は身の丈がサイアリーズほどもない小人……というかドワーフそのものといった男だ。
「あなた達が逃がし屋のログ、ですか?」
アルシュタートが彼らに向かって言った。無精ひげの男が、がははと笑う。
「ああそうだ。正確に言うと、ログとガン公だな」
「……それも正確違う。俺、ガンデ」
「ガンデさんと、ログさんですね。妾はアルシュタート=ファレナス。ラージャ様からの紹介で参りました。そなた達は腕のよい逃がし屋だそうですね。妾たちを、ソルファレナに連れて行って頂きたいのです」
「ソルファレナ? しかもファレナスってあんた姫さんが王宮に帰るのになんで逃がし屋が必要なんだよ」
「それは……」
アルシュタートは事情を簡単に説明した。ログとガンデは真剣に聞いていたようだが……。
「あーなんだ、とにかくソルファレナの下水まで道を通して、中にいれてやりゃいいんだな」
「それ、説明しない状態とあまり替わらない気がするんだけど」
キサラの冷静なつっこみに、ログがううんとうなった。
「だってさー、俺バカだもん。王様やお姫様の複雑な事情なんてわかんねえよ」
「だったら聞かなきゃ良いじゃない」
「こ、こんなに複雑な話だと思わなかったんだよ! 俺のとこに仕事持ってくるのは、たいがい高利貸しに騙された奴とか脱獄したい奴とかそんなもんなんだから!」
ログはわめく。ふう、とアルシュタートはため息をついて口を挟んだ。
「それで、仕事は受けてくれるのですか?」
「そうだなあ。どうする? ガン公」
「ソルファレナの下、滅多に掘れない。……女王様の許可あるなら堀りほうだい」
ガンデは至極嬉しそうにうふふ、と笑った。ツルハシを握る手が小刻みに震えている。
「が、ガン公……」
「あの、ガンデさん、私は姫であって女王様ではないので、堀りほうだいというわけでは……!」
アルシュタートが止めるのも聞かず、ガンデはそのまま洞窟に向かっていってしまった。
「お、おいガン公!! ……しょーがねえなあ。相方がやる気なんじゃ乗るしかないか。いいぜお姫様。俺たち二人、あんたらを王宮まで連れて行ってやろうじゃないか」
「ありがとうございます、ログさん」
「おう、別嬪さんのお願いはきくのが一番だからな!」
ログは、顔一杯を笑顔にするようにして笑った。どうやらこれで、王宮まで乗り込むのに必要な駒はそろったらしい。
「で、どれくらいで中に入れるんだ? ガンデのほうはやる気のようだが」
一口に抜け穴、というが、穴を掘る作業というのはなかなか簡単にできるものではない。
「あー、ちょうど北向きの道ができてたところだからな。ガン公の腕ならラージャの読みどおり二日で抜け穴ができるだろ。だけど、街にも敵がいるかもしれないんだろ? 女王様の前まで行けるように、もう一工夫考えないとだめだろうな」
「もう一工夫か」
「それを手配するのが俺の役目だ。そうだな、ちっと腰を落ちつけて話すか。こっちに部屋があるから来てくれ」
ログは手招きをすると洞窟の中に入った。後を追っていくと、道の脇にドアが作りつけられている。
「入ってくれ」
ログに促されて中に入ったそのドアの先には部屋というより巣と言ったほうがいいような空間が広がっていた。
広さはちょっとした宿屋の一室くらいのものなのだが、やたらと荷物(というよりがらくたが多い)が置かれていて狭っ苦しい。その上片づけをしていないものだからそこら中ゴミだらけの埃だらけだ。
「……何ここ」
キサラがくっきりと眉根に皺をよせる。
「あー、俺のねぐらだ。前の仕事で使った小道具をそのままにしてるからちょっとばかりちらかってるが、問題ないだろ」
問題ありまくりだ。
少女三人はそうつっこみたいのを抑えてログを睨んだ。
何しろ、この部屋は汚い。
黴が生えた食器が転がっているのには言うに及ばず、置きっぱなしで発酵しているとしか思えない座布団に汚れがこびりついたテーブル。そして壁を埋め尽くすように配置された意味不明の小道具の数々。こんな部屋で腰が落ち着く女がいたらお目にかかって見たいものである。
「ここを開けたら座れるかな?」
その視線には気づかずに床のゴミをよせて、ログは小汚いテーブルの周りに人の座るスペースをつくっている。
が、場所を選んでいる状況でないのも確かだ。
一人で勝手に座ってきょとんとしているログに苦笑して、フェリドはその向いに座った。そしてゴミの山を睨んでいる少女のうち、一番幼い少女に声をかける。
「床に座るなら俺の膝に座るか? サイアリーズ」
「いいの? お兄ちゃん」
あぐらをかいたフェリドが膝を叩くと、サイアリーズが嬉しそうに膝に座った。フェリドはサイアリーズの頭をぐりぐりなでるとアルシュタートを見る。
「アルシュタートも座るか?」
一応、フェリドの膝はまだあいている。
しかし当然ながらアルシュタートはぷいと横を向いた。
「嫌です。そんなはしたないことをするくらいなら床に座ります」
どすん、と音がするくらいの勢いでアルシュタートは床に座る。今度はログが膝を叩いた。
「キサラ、あんたはどうだ?」
「床がいいわ。あんたの膝、床より汚れてそうだもの」
キサラも座ったところで、ログが渋面になる。
「……気ぃ強いよなぁ」
「確かに」
フェリドも苦笑すると、キサラとアルシュタートに同時に睨まれた。
「そういう問題じゃないわ。それより、王宮に乗り込む方法を考えるんでしょ?」
キサラが言うと、おお、とログが答えた。
「そうだったそうだった。えーと、王宮の地図、地図っと……あったかな……あーこれだ」
がらくたの中をごそごそと探し回っていたログは、その下のほうから紙切れを一枚取り出した。扱いが悪いせいで汚れているが、ソルファレナの建物を記した地図のようだ。それをフェリド達の前に広げると、懐からナッツをいくつか出して地図の上に載せる。
「下水道の出口は、ここと……ここと……ここだ。姫さん、あんた王宮に入れる抜け道があるって言ってたな。それはどこだ?」
「ここです」
アルシュタートは王宮の西側の壁の一点を指さす。ログはまたナッツを取り出してそこに置いた。フェリドはその位置関係を眺める。
「ふむ。それだったらこの出口から出るのがよさそうだが……ゴドウィンの見張りがいるだろうな……アルシュタート、あんたがここに見張りをたてるなら、どこに配置する?」
「そうですね……ここと……ここと……ここでしょうか?」
再びアルシュタートが指し示した位置にナッツが置かれる。
一同は地図の上に置かれたナッツを眺めて、同時に軽いため息をついた。ややあって、ログが息を吐いて言った。
「これだと、見張りが邪魔だな。どうしても入るときに見とがめられる」
「一人倒してそのすきに中に入ってもいいが……この位置関係だと仲間が気づくな」
「何かで気をそらすことはできませんか?」
「爆竹みてぇなものならあるが……一瞬の音じゃあちょっと間合いが足りねえな。少し注意を惹きつけて移動させるくらいのことをしないとだめだろ」
ぼりぼり、と無精ひげをかきながらログが言う。
フェリド一人ならそれで十分の間合いだが、少女二人を抱えているのではそうはいかない。
「じゃああたしがおとりになるわ」
ややあって、キサラがそう提案した。
「キサラさん!」
「私と姫様なら、体格も歳もそんなに変わらないから、かつらをかぶって姫様の服を着れば暗殺者達の目を惹きつけることができるんじゃないかしら」
「だめです! そんな危険なことさせられません」
アルシュタートが怒鳴った。しかしキサラはにっこりと笑う。
「いいんですよ姫様。あたしだってラフトフリート一番の船乗り、そこらの兵士よりは強いです。それにファレナのために死ねるなら本望ですわ」
「安易に死を覚悟することはファレナのためにはなりません。それに、民のために命を賭すことこそが王家の勤め。自分のために民の命を危険にさらしたくはありません」
「なかなか嬉しいことを言う姫さんだな」
ログが感心して口を開けた。
「……そのぶん融通がきかんがな。しかしどうする?」
「やっぱりキサラにおとりをやってもらうしかねぇだろ」
「ログさん!」
「ただし、キサラに護衛をつける」
「おい……」
「わかってるって、フェリドの旦那。王宮に入れたとしてもまだ何かあるかもしれないからな。あんたは姫様達の護衛にずっとつかなきゃならねえ。護衛につくのは俺ってことさ」
ログは無精ひげだらけの顔でにやっと笑うと、どん、と胸を叩いた。
「こんな別嬪さんをおとりに仕立て上げて放り出した、なんてしれたら逃がし屋ログ最大の恥だ。俺がキサラを安全なところに逃がしてやるよ。それでいいだろ?」
逃げるのには悪くない地形だしな。
ログはそう言って、地図にまた目を戻した。
「ここに船着き場があるだろ? ここにあらかじめ流れの紋章を仕込んだ小舟を用意しておいて、やつらを惹きつけたところで飛び乗って逃げればいい。周りの船を使えなくしておけば、そう簡単に追いついてこれない。どうだ? 姫様」
「……それは」
「大丈夫だって! 俺もキサラももちろん死にたくねえ。逃げるとなりゃあ必死で逃げて生き残ってみせるからよ」
「民を信じるのも王家の勤めじゃないのか?」
フェリドがぼそりと言うと、アルシュタートはやっと頷いた。
「そう……そうですね。キサラさん、ログさん、危ない役目ですが、やって頂けますか?」
「あったりめえよ!」
「姫様のために生き残って見せますわ」
ログとキサラに元気よく笑いかけられて、アルシュタートは泣き笑いのようなほほえみを浮かべた。
「ありがとうございます……」
「礼は無事王宮に入れてから言ってくれ。よし、そうと決まれば準備だ準備! キサラ、あんたの船の流れの紋章貸してくれ」
「かっこいいこと言ったとおもったら、あたしの船の紋章をあてにしてたの? しょうがないわね。あとで返してちょうだいよ」
「おう、もちろんだ。じゃあ俺たちは小道具の調達に行ってくるから、旦那と姫様達はそこで休んでいてくれ」
がはは、と笑うとログはキサラを連れて出て行った。部屋の中にはフェリド達だけが残される。
「なんとか……王宮に入れそうですね」
「多分な。あの逃がし屋も船乗りも腕は悪くない。……が。サイアリーズ、すまんが膝から降りてくれ」
「えー?」
サイアリーズは、口をとがらせながらフェリドの膝から降りる。フェリドは立ち上がるとアルシュタートに手をさしのべた。彼女も立ち上がる。
「フェリド?」
フェリドは、二人をドアの近くへ押しやってから振り向いた。
「さっきの作戦、変更したほうがよさそうだ。ネズミが一部始終聞いていたようだからな」
少女達二人を背にかばい、フェリドは鞘から剣を抜きはなった。少女達は、わけがわからないなりにフェリドの後ろにぴったりとつく。
フェリドは油断無く構えながら、部屋の中にある棚を睨み付けた。
「……やれやれ、勘の良すぎる人は嫌われますぜ」
すう、と部屋の中の闇が人の形をとった。いや、闇の中から人が姿を現したのだ。
「これでも気配を隠すのは得意中の得意だったんですがねえ」
のんびりとした口調で、その人物はぼやく。
「腕は悪くないと思うぞ? この俺が今の今まで気づかなかったくらいだからな」
「お褒めに預かり光栄ですね」
ずいぶんと痩せた男だった。
拳を叩きつければすぐに折れそうな見た目だが、闇が凝ったような鈍い色の瞳がそれを裏切っていた。
「誰だ、お前は」
「シナツと申します。幽世の門……と言えば後ろのお姫様はわかりますかね」
フェリドの背後で、アルシュタートが息を飲んだ。体をこわばらせ、全身を緊張させる。
「……おい、なんだそのカクリヨってのは」
「女王直属の暗殺部隊です」
「ってことは敵か」
フェリドは、いつでも剣を叩きつけられるように油断無く足の位置を整える。
しかし、暗殺者はらしくなく慌てた。
「ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいよ! あたしは敵じゃないですってば! 旦那もわかるでしょ? 旦那が本気出したらあたしなんか敵わないってことくらい。それでも姿を現したってことを少しは汲んでくださいよお」
シナツはあわれっぽく訴えかけた。
まさか、暗殺者に命乞いをされるとは思わなかったフェリドは少しだけ殺気をゆるめる。
「だいたい、私は暗殺向きの人間じゃないんですよ。情報を集めるのが本業で。荒事なんか避けて通るのがモットーなんですから」
「……変わった暗殺者だな」
「まあねえ。暗殺も最近は情報がないとやってられませんから。情報の専門部隊が必要なんですよ」
「私たちが生きているという情報をゴドウィンに売る気ですか?」
アルシュタートの鋭い言葉に、シナツはいえいえ、と手を振る。
「貴方も言ったじゃないですか。幽世の門は女王直属の暗殺部隊だって。私はね、ゴドウィンでもバロウズでもなく、現女王オルハゼータ様の命令で貴女方を捜していたのですよ」
「敵ではない、と?」
「私の言葉を信じて頂けるなら」
「……だいぶ無理なお願いだな」
「私もそう思います」
シナツは、開き直ったのかへらへら笑っている。
「よく、俺たちの先回りができたな」
「まあそこは蛇の道は蛇……いろいろと手があるものです。でもご安心を。ゴドウィンの連中はまだ気づいておりませんから」
「ほー。よかったな、アルシュタート、夫婦ごっこも役にたったみたいだぞ」
「役に立ってなかったら貴方を殺してます」
二人のやりとりを見て、シナツはくつりと笑う。暗殺者のくせに、この男はひどく人間くさい。
「で? 女王直々の調査の結果、生きてることがわかったんだ。さっさと報告してここに女王の迎えをよこしてくれよ」
「そうはいきません」
「何故だ?」
シナツはやれやれとため息をつく。
「所詮あたしは胡散臭い暗殺部隊の一人ですからね。表向きにはいない人間なんです。そんな人間が報告してきたからって、女王陛下が軍を動かしたり葬儀をとりやめたりすることはできません」
これは本来ないはずの情報なのですから。
つまり、結局自力で帰ってこいということだ。シナツの言葉に、フェリドが息を吐く。
「なんだ。子供の使いより役にたたないな。意味のない情報を報告するだけか」
「旦那も言いますねえ。痛いところだ」
す、とシナツは身をひいた。
「確かに公に迎えを連れてくることはできませんがね、暗殺部隊なりのお役目というものがあります。貴女方が王宮に戻る手助けをすることはできますよ」
「おい」
「期待していてください。こっそりとですが、確実に貴女方をお守り致します」
男は再び棚の裏に身を隠そうとしていた。
相手の意図に気がついて、フェリドが追う。しかし、シナツが隠れたはずの棚の裏にはもう誰もいなかった。
王都ソルファレナ。
太陽のごとき威光と大河のごとき慈愛をあまねく示すというファレナ王家のスローガンをそのまま表現するこの都市は美しい。
王宮を中心に放射状に広がる道を起点として、計画的に整備された街には様々な商店が建ち並び、巡らされた運河の水は澄んで整えられ、人の生活を潤している。
普段は多くの人が行き交い、運河には小舟がいくつも出ている明るい都なのだが、ここ数日は暗く沈んでいた。
女王オルハゼータの孫、アルシュタートとサイアリーズが殺害されたからだ。
殺したのは、暗殺者。
彼女たちを邪魔に思う貴族の仕業であろうと裏で囁かれていたが、まだ犯人はわかってはいない。
罪もない少女達の命を奪った凶行に、人々は憤りと悲しみの入り交じった感情を抱いていた。
だが、悲しみにくれるばかりでは国は立ちゆかない。
王家は昨日到着した遺体を祭壇に捧げ、早くも本日葬儀を執り行っていた。
王家の儀式が終わったあとは、民が参列し、冥福を祈る。幼い姫君達へ供える花を人々が用意しながら、王宮の門が開くのを待っていたときだった。
王宮を取り囲む西側の塀の前で、奇妙な声があがった。
「あれー? 姫様?! アルシュタート姫様がいるぞ?! 死んだはずじゃなかったのか?」
叫んだのは、無精ひげの男だったか。
だがしかし、叫んだ者のことなど、人々の記憶からすぐに消し飛んだ。
そこには、高貴な衣装に身を包んだ、銀髪の少女がいたからだ。
「姫様?」
「姫様?!」
人々がざわざわと騒ぎ始める。少女は、衣を翻すと、塀より更に西の船着き場へと走り出した。
「行った……みたいだな」
繁みに隠れていたフェリドは、騒ぎの行方を見届けながらつぶやいた。
アルシュタートの格好をしたキサラはログに守られながら、船に乗ったようだ。彼女の操舵技術なら、無事に逃げおおせるだろう。
「では、こちらも行きましょうか。サイアリーズ、走れますか?」
「大丈夫だよ! 姉上よりも早く走るんだから」
変装したアルシュタートとサイアリーズが壁の一角を押す。すると、地面に人一人がやっと入れるくらいの小さな穴があいた。
「地下道になっています。まっすぐいけば、厨房の近くに出ます」
「わかった」
フェリドは頷くとまず穴に入った。中で明かりをともしてみる。道は、まっすぐ王宮の中心部へと続いているようだった。
「キサラさんとログさんの努力を無駄にできません。急ぎましょう」
後から続いて入ってきたアルシュタートが囁く。フェリドは頷いた。
彼らは、作戦通りに囮を使って抜け道へとやってきていた。シナツの出現で、情報が漏れたかに思われたが、その後彼らの計画を知ったものからの妨害もなかったのでそのまま実行したのだ。(他に策も手駒もなかったとも言う)
それに、シナツの見せた妙な人間臭さが、フェリドに彼を信用させていた。
「アルシュタート、あんたはサイアリーズの手をしっかり握っていてくれ。サイアリーズ、姉上から絶対に離れるんじゃないぞ」
「うん!」
フェリド達は走り出した。
この先に、やっと彼女たちが帰る場所がある。
気を抜きそうになったフェリドは、その直後に考えが甘かったことを思い知らされた。
「アル! 止まれ!!」
後ろから来るアルシュタートを止めると、フェリドは火種を彼女に渡した。剣を引き抜いて、構える。
ひたひたと訓練されたことがよくわかる足音をさせて、前方から複数の人間がやってきていた。
「壁にはりついてろ!!」
言って、駆け出す。
闇の中、勘を頼りに繰り出した剣は、一撃で相手の命を絶った。続いて来る敵も切り倒して突き飛ばす。
「く……」
アルシュタートの様子を見ようと振り返ったフェリドは、彼女たちの更に後方から足音が近づいてきているのを感じた。冷や汗が背中を伝う。
暗殺者はそう強くはない。
フェリドの敵ではないと言ってもいいだろう。
だが、この狭い通路で彼女たちを守るにはフェリドの手が足りない。
(やはり、あの男を信用して作戦を変えなかったのはまずかったか)
無理矢理にでも前方に進もうとしたときだった。
「あぁ、ひどいな旦那。今私のことを疑ったでしょう?」
闇から、声が響いた。
そして後方から追ってきていた暗殺者の気配が消える。
「シナツか?」
「はいはい、そうですよ。私です。旦那、抜け穴を使うのはいいですが、入ったあとにちゃんと閉めておかないといけませんよ? すぐに道が発見されて追っ手が来ちゃいますから」
「……そういうことか」
一切姿を見せないところは、暗殺者そのものだというのに、闇から響いてくる、声は相変わらず妙に人間臭い。
「手助けすると言いましたからね、後方の敵は私にお任せください。旦那は姫様を連れて先へ」
「荒事は避けるんじゃなかったのか」
「たまにはサービスということで」
「そうか」
フェリドは剣を構え直すと前方の敵に向かった。アルシュタートが走りながら、顔だけ振り返る。
「ありがとうございます……シナツ」
「ありがとぉ」
「よしてください。お姫様に感謝される身分じゃありませんから」
彼女たちの背後では、フェリドほど派手ではないが、静かに戦闘が行われている。アルシュタートは小さく頭を下げると、先を急いだ。
「フェリド!」
「おい、やっと出口らしいところまでたどり着いたんだが、ここから出ればいいのか?」
死体に躓きつつ、二人がやっとフェリドの背中に追いつくと、そこには簡素な扉があった。
「はい、開けてください」
フェリドは、警戒しながら扉をあけた。見渡すと、細い廊下の奥であることがわかる。
辺りから漂う食事の臭いが、彼女の言うとおりここが厨房の近くであることを示していた。
「ここから葬儀の場所まではどれくらいだ?」
「すぐです。行きましょう」
アルシュタートは、変装のためにかぶっていたフードを取り払った。サイアリーズと二人、王家の血筋を示す銀の髪がさらされる。
「この先は、妾のことを見知っている者ばかりです。声をかければ道をあけてくれるでしょう」
「そううまくいくといいがな」
フェリドは剣を鞘にしまうと、葬儀が行われているはずの謁見の間の方向を見やった。進むと、当然ながら衛兵がやってくる。
「おい、お前達! どこから入った!!」
衛兵の一人が声をかけた。アルシュタートが前にでる。
「お下がりなさい。妾の顔を見忘れましたか?」
「あ、アルシュタート様? サイアリーズ様も?!」
衛兵達は足を止める。驚くのは当然だ。今まさに彼女達の葬儀が行われているはずなのだから。
「そこを通してください。このばかげた葬儀を終わらせます」
「しかし……」
「ちょっと待てよ、本当にあの人姫様か? 葬儀にかこつけてやってきた偽物じゃないだろうな」
衛兵のうちの一人が、そう言って睨み付けた。周りの兵が動揺する。
「え……?」
「すみませんが、葬儀は大事な儀式、偽物を通して騒ぎを起こすわけにはいきません。こちらの奥の間で本物の姫様かどうか確認させていただけますか」
疑いをかけた兵士は、一歩前にでる。
その様子には、妙に迷いがなかった。そう、まるでアルシュタート達が現れた時の答えを用意していたかのように。
フェリドはアルシュタート達を背にかばった。
「あの兵士もゴドウィンとやらに抱き込まれてるみたいだな。どうする? 確認されておくか?」
「そんな暇はありません」
「だよなあ。突破するからついてこいよ」
「お願いします。けれど」
「殺すなってことだろ? わかってるさ。こいつらのほとんどは何も知らない真面目な兵士だ」
フェリドは剣を鞘から出さずに拳を構えた。
近衛兵達は、一般兵よりは強いが蹴散らせない相手ではない。まず一人目に一撃を食らわせようとした時だった。
「何事だ」
重く、威厳のある声が廊下に響いた。
その声のもつ力に、今まさに戦闘が行われようとしていた廊下がしんと静まりかえる。
「何事だと、訊いている」
再度問いながら廊下に現れたのは、壮年の騎士だった。
黒と金を基調とした豪奢な鎧に純白の飾りたすき。その威風堂々とした様子から、他の兵達と全く格が違うということがわかる。
「ガレオン様! この偽物達が……」
「偽物? お前は目が悪いのではないか? アルシュタート姫様とサイアリーズ姫様だろうが」
「しかしお二人は死んだはずです!」
「ここに生きた姫様達がいらっしゃるのだ、そもそもお亡くなりになったということ自体が間違いなのだろう。もうよい、お前達は下がれ」
「しかし」
「下がれ、と言っている」
騎士の威圧感に耐えられなくなったのか、近衛兵達は一礼してその場を去っていった。
ガレオンはゆったりとフェリド達の前に歩み寄り、その場に跪く。
「お帰りなさいませ、アルシュタート姫様、サイアリーズ姫様。よくぞご無事で……」
「ガレオン!」
サイアリーズが、騎士に飛びついた。アルシュタートも跪く騎士に手をさしのべる。
「ガレオン、ありがとうございます。おかげで兵達を傷つけずにすみました」
「いいえ、お礼など。王家の方々をお守りする女王騎士でありながら、この程度のところまでしかお迎えにあがれず、申し訳ありません」
「よいのですよ。さあ顔をあげてください」
「はい」
「迎えに来たってことは……あんたここに二人が来ることがわかってたのか?」
「女王陛下から、厨房に亡霊が現れるやも知れぬため、見張っていろとのご命令をうけまして、ずっと待機していたのです。陛下からご命令を頂いたときには、もしやと思いましたが、生きた姫様方にもう一度まみえることができるとは……」
騎士はくしゃりと顔に皺を寄せて二人に笑いかけた。本気で心配をしていたその表情に、フェリドもやっと警戒心を解く。それを見て、ガレオンが苦笑し再び頭を下げた。
「貴方が、姫様を守ってくださったのですね、ありがとうございます」
深々とした丁寧な礼にフェリドが慌てる。
「そういうことは、女王の前に二人を連れて行ってやってからにしてくれ。葬儀のほうはずいぶん進んでいるんじゃないのか?」
「その点はご心配なく。まだ、間に合います。では姫様行きましょう。そちらの……」
「フェリドだ」
「フェリド殿もご一緒に。女王陛下がお待ちです」
ガレオンは、三人を先導して歩き始めた。
謁見の間に近づくにつれ、すれ違う人間も増えたが、ガレオンの有無を言わさない雰囲気のせいか、死んだはずの姫二人と怪しい傭兵くずれという道連れに、誰も口を差し挟まなかった。
しばらく歩いて、ようやく真っ白な扉の前に出た。奥からは、厳かな音楽が静かに流れてきている。
ここが最終目的地の、謁見の間。
「お入り下さい」
ガレオンが音も立てず重々しいドアを開いた。
豪奢なステンドグラスから差し込むまぶしい光と、列席者達の驚愕の視線が四人を迎えた。
どよ、という一瞬のざわめき。
そのあとは時間が止まったかのような沈黙が部屋中を支配した。
アルシュタートとサイアリーズの二人だけが、その沈黙の支配から逃れて悠々と祭壇へと進んでゆく。
祭壇の前には、三人の女がいた。
中央に立つ、黄金の冠を頂いた銀の髪の老婆。老婆の右に立つ、驚愕と憎悪の表情を浮かべた壮年の女。そして老婆の左に立つ、喜びに満ちた表情の壮年の女。
三者三様のその表情と立ち位置は、まるで絵に描いたように彼女たちの立場を現していた。
アルシュタートとサイアリーズは、老婆の前で優雅に礼をする。
「おばあ様、アルシュタート=ファレナス、ただいま戻りました」
「サイアリーズ=ファレナス、ただいま戻りました」
「おかえりなさい、アル、サイア」
老婆はにっこりと微笑んだ。その動作に、列席者の間でざわざわとしたどよめきが復活する。
「アルシュタートとサイアリーズですって? 二人は死んだはずです! そなた達は何者なのです!」
老婆の右に立っていた憎悪の女が叫んだ。
すう、と老婆が女と姫達の間に入る。
「おだまりなさい、シャスレワール」
「しかし母上!」
「妾が孫の顔を間違えるわけがないでしょう? この子達は確かに妾の孫です。この祭壇で弔われている遺体が間違いなのですよ。ファルズラーム、いらっしゃい。貴方の娘が帰ってきましたよ」
老婆が言うと、左に控えていた女がアルシュタートとサイアリーズに抱きついた。
「アルシュタート……サイアリーズ……!! 死んだと聞いて、母はもう……」
「母上……」
ぼろぼろと泣き崩れる母親に、姫達もまた彼女を抱きしめ返した。女王は列席者にほほえみかける。
「さあ、悲しい祭りはこれで終わりです。この子達は、ちゃんと本来の名前で弔ってあげましょう」
女王の言葉に、列席者達の半分ほどが歓喜の声をあげ、残り半分が歓喜ともため息ともつかぬ声をあげた。恐らく、この歓声の温度差がそのままこの国の貴族達の勢力図となっているのだろう。
ひときわ高く歓声をあげている集団の中から、男が一人走り出てきた。
でっぷりと太った体と、派手苦しい格好からいかにも貴族らしい嫌な空気を放っている。
「恐れながら女王陛下。葬儀という祭りを取りやめるだけでは足りません。この沈んでしまった空気を払拭するために、新たな祭りを執り行うべきではないかと、思います」
「何です、バロウズ郷?」
女王は男を見下ろした。
「闘神祭ですよ、闘神祭! 国を盛り上げるためにこれほどよい祭りはないでしょう」
「しかしバロウズ郷……それは却下したはずです」
「今回の騒動でおわかりになられたでしょう? アルシュタート姫様をつけねらう者は多いのです。たまたま無事だったからよかったものの、再び危険な目にあう可能性はあります! 姫様には強力な後ろ盾が必要なのですよ」
「お待ちなさい!」
憎悪の女……シャスレワールがまた怒鳴った。
「年齢からいけば、妾のハスワールが先です」
「お歳の問題ではないのですよ、シャスレワール様。問題はこのような事件が起きたこと、今後このようなことを起こさないために何ができるかということです」
「ぬけぬけと……」
「お下がりなさい、シャスレワール」
「母上!」
女王は重々しくため息をついた。
「闘神祭を執り行いましょう」
静かな女王の宣言に、謁見の間は再び一瞬静まったあと、歓声とどよめきに包まれた。
深夜。
夜尚明るいソルファレナであっても、人々が寝静まるほどの時間帯。
自室の窓からぼんやりと月をながめていたアルシュタートは、異様なものを見て、危うく悲鳴をあげそうになった。
「ひっ……!」
精緻なステンドグラスに彩られた王族の私室、その窓の下から、にょっきりと人の手がのびていた。誰かが壁をよじ登ってこの窓まで来ている。
そう理解したアルシュタートは、すぐに窓際に駆け寄った。
その手が見覚えのある人物のものだったからだ。
大きくてたくましい、剣を持つための手。
「フェリド……?」
窓を開けると、フェリドが顔を出した。
悪戯が成功した子供のような顔で笑っている。
「……な、何をしているのですかっ、そなたはっ……」
「不法侵入」
「……見つかったら殺されますよっ! は、早く中に!!」
アルシュタートは、フェリドを引っ張り上げると大あわてで窓を閉めた。そして、窓から死角になる場所へと連れてきて座らせる。
「そなたには客用の部屋が与えられたはずですよ。何故ここに?」
「あんたと話がしたかったから」
「話って……明日になればまた話せます」
「本当に?」
ひょい、と顔をのぞき込まれてアルシュタートは言葉を無くした。
「明日になったら、あんたはここのお姫様で、俺はよそ者だ。ゆっくり話なんてできないだろ。俺は、あんたと二人で話がしたかったんだ」
「え……妾と……二人で?」
どうして、という言葉はアルシュタートの喉の奥にしまいこまれた。フェリドがアルシュタートの手を引いたからだ。その手に引き寄せられるようにしてアルシュタートはフェリドの隣に座る。
「なあ、闘神祭って何なんだ? 折角帰ってきて、親にも周りにも守られてるはずなのに、あんたの顔色が悪いのは何故なんだ? なんで、そんなにつらそうなんだ」
まっすぐに見つめられて、アルシュタートは俯いた。
「アル……」
「闘神祭は、この国の伝統の儀式の一つで、王家直系の姫達の婿を選ぶために開催される闘技大会です。この闘技大会で優勝した者が、姫の夫となり、姫が女王となった暁には、その夫が女王騎士長となります」
「……な……に? 婿選び……だとぉ?」
「この大会では貴族が代理人をたてることが認められているため、闘技大会とはいえ実際に女王の婿として迎えられる者は有力な貴族であることのほうが多いのです。私の母も、叔母も、祖母もそうでした」
「ちょっと待て、お前のための闘神祭、ってことはあんたの婿を選ぶのか?」
「そうです」
こくりとアルシュタートは頷いた。フェリドが驚いて目を丸くする。
「そりゃ早すぎるだろ?! あんたどう見たって15かそこら……」
「失礼なことを言わないでください! 私は今年で18です!!」
「何?! 俺と4つしか違わないのか?!」
「ええ? そなた、まだそんなに若かったのですか?」
珍しく、フェリドが言葉に詰まった。
「…………老けて見られる方だが……まだ22だ。いくつだと思ってたんだ」
「お聞きに、ならないほうがいいと思います」
30以上だったらただじゃおかん、フェリドは小さくつぶやいた。
「まあ歳の話は横に置いておくことにするか。それで? 要は婿をとるための祭りをやるって……ことなんだな?」
「そうです。本来従兄弟のハスワールのほうが四つ年上で先に闘神祭をやるべきだったのですが、母の後ろ盾であるバロウズ郷が強くおばあ様に開催を要請していたのです」
「前から、話があったのか?」
「ええ。ですが、この対立している状況で闘神祭を行えば争いの火種となります。だからロードレイクの別荘に避難していたのです」
「しかし、そこへいっそ殺してしまえっていう過激な連中がやってきて、必至で戻ってきたら更に事件が徒になった、ってことか」
ふう、とフェリドがため息をついた。
何故彼女がロードレイクにいたのか、何故母親の後ろ盾であるバロウズ家に助けを求めずラフトフリートに向かったのかがわかった。
アルシュタートは、どちらの家の権力闘争にも関わり合いたくなかったのだ。
「今、ファレナはゴドウィンとバロウズと間に入るロヴェレ家によって危ういバランスをとっています。闘神祭でどちらの代理人が優勝しても大規模な闘争が起きるでしょう」
「なあ、いっそバロウズともゴドウィンとも違う勢力の人間が優勝したらいいんじゃないか? そうしたら、勝負はドローだ」
「それは難しいでしょう。この国の貴族であれば、両家に何らかの関わりを持っています。国外の方であっても、何かを背負っている方が多くて……」
「俺じゃだめか?」
フェリドは俯くアルシュタートの顔をのぞきこんだ。しかし、アルシュタートは身をひいて首を振る。
「そなたではだめです」
「俺はこの国の権力争いに関係ないし、何よりあんたの味方だ。悪くないと思うが?」
「そなたにも、背負うべき民があるはずです。妾の国の民を背負わせることはできません」
「背負うべき民って……俺はそんな大層な身分の者じゃあ」
「群島諸国連合艦隊提督スカルド=イーガン様の次男、フェリド=イーガン殿。それがそなたの正体ですね」
ぴたり、とフェリドの動きが止まった。
隠していたはずの身分を言い当てられてフェリドが呆然とする。
「いつから……知ってたんだ?」
「群島諸国のお話をしてくださった辺りから。それに、一度会っただけですがそなたは本当にスカルド提督によく似ていらっしゃいます」
「あんのオヤジ……そういえば来てたんだったか。だけどな、アルシュタート。それは気にしなくていい。どうせ跡取りは兄貴ともう決まってるんだ。風来坊の次男が婿に行っても問題ない。むしろ家族連中は笑って祝福するぞ」
「ですが、これは王女との婚姻です。貴方の群島諸国を、妾の国の権力闘争に巻き込んでしまいますよ」
「だったら国なんか捨てるさ。身分も適当に隠して、ただの傭兵フェリドとして出場する。それなら問題ないだろう」
「国も身分もって、そなた今までの人生を捨てる気ですか?!」
「ああ。惚れた女のためなら、人生も身分も捨てて構わん」
「惚れた……って、フェリド?」
アルシュタートが絶句した。フェリドも言ってしまってから言葉の内容に気づいたらしくあらぬ方向に視線を泳がせる。
「あー……恥ずかしい話をするが…………アルシュタート」
「……は、い」
「本当のことを言うとな、一目惚れなんだ」
フェリドは一回首を振ると、アルシュタートをまっすぐに見つめ直した。その顔は青白い月光に照らされていてさえ尚赤い。
「俺に、お前を守らせてくれないか?」
ゆっくりと、アルシュタートの頬に触れる。アルシュタートはその手に自分の手を添えた。
「実は、闘神祭の開催が宣言されてから、ずっとどうやって逃げようか考えていたのです。それから、どうやったら群島諸国へ帰るそなたを追っていけるのか」
「アル……?」
「王女としてはいけない考えだとわかっていたのに」
おずおずと、ぎこちない仕草でアルシュタートは顔をあげた。やっとアルシュタートの瞳がフェリドを見つめる。
「妾を、守ってくれますか?」
「ああ。あんたのために、勝利をつかもう」
フェリドは笑うと、アルシュタートの唇に誓いの口づけを落とした。
その一月後、王女アルシュタートの推薦をうけた謎の傭兵が闘神祭で優勝し貴族達の闘争を中断させたことは有名な逸話である。
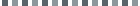
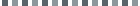
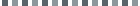
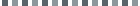
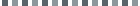
勢いだけで描き始めたフェリド×アルシュタートSS(ねつ造過多)です。
長い! 長いよ!!
あんたどこまでプロット広げるつもりだよ!!
途中何度か気が遠くなりかけました……
うう、でも書きたかったんだもん。
書きたかったんだーもーんー!!
(わがままかよ)
ああでも、若くて不作法者のフェリドさんとか、
怒りっぽい女王様とか書けて楽しかったです。
誤算は思いつきで出したオボロさん(暗殺者時代)でしょうか
出したらえらくでばってしまって笑うしか……
好きキャラはどーにもなりませんな。
ちょこっとおまけ
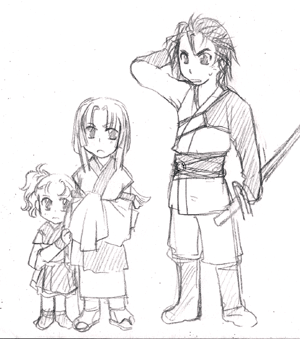
22歳フェリドと、18歳アル。
でもって9歳サイア
あんだけグラマラスなアルシュタート様が、
昔スレンダーだとおもしろいなとひたすらネタに(おい)
も一つおまけ
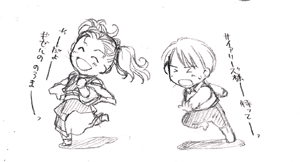
9歳サイアリーズと、7歳ギゼル。
婚約解消されてぐれちゃうまでは、サイアリーズに振り回される素直なよい子だといい。
>戻ります