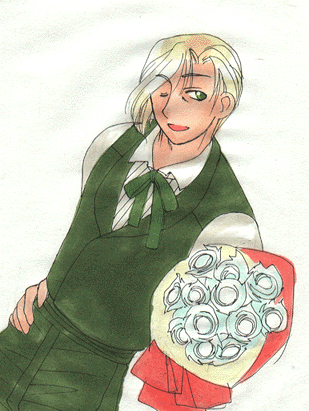
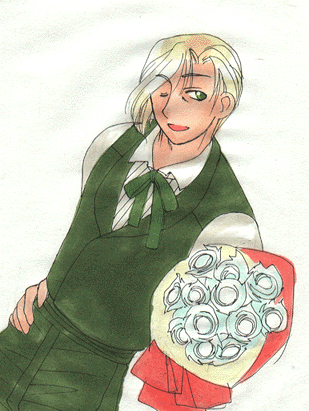
「う〜〜〜〜〜〜〜んん」
交易所のショーケースを睨みながら、俺はうなっていた。
「ナッシュさん、いいかげん決めましょうよ」
店主のスコットは心配そうだ。それも当然か。なにしろ、俺はかれこれもう一時間以上も悩んでいるのだから。
本日は三月十四日。
いわゆるホワイトデーだ。
先月、お仕えする女王様からチョコレートを賜るという栄誉に預かった下僕の俺(言ってて少し悲しい)は、お返しを購入すべく店にやってきたのだが……プレゼントが決まらない。
「どっちもいいんだよなあ」
むう、と悩む視線の先には、二対のピアス。両方とも銀細工で、小さな月に丸い石がくっついているというデザインだ。両者の違いは、ついている石。片方は神秘的なアメジスト。もう片方は血のようなガーネット。
どちらも上品で、どちらも女王様に似合いそうだ。
ただし、両方買う金はない。
「奥さんが使いやすそうな色の石にしてみたら?」
「それが、こっちのガーネットはカミさんの瞳の色で、こっちのアメジストはカミさんがよく着る服の色なんだ。使い勝手はほぼ同じだと思うんだが……」
「じゃあどっちでもいいじゃない」
「う〜〜〜ん」
人はそれを優柔不断と呼ぶ。
やれやれ、とスコットがため息をついたとき、店の戸が開いた。
「すいません、スコット殿、頼んでいた品物は届きましたか……って、ナッシュ殿何やってるんですか?」
「見ての通り、カミさんにプレゼント買ってるんだよ。パーシィちゃん」
「貴方にその呼び方で呼ばれたくないです。やめてください」
がしゃがしゃと甲冑を鳴らしながら店に入ってきたのは疾風の騎士と誉れ高いパーシヴァル・フロイライン殿だった。今日も髪が美しくなびいている。
「プレゼントはわかりますが、その格好は一体何なのですか?」
パーシヴァルは不審そうに俺を見る。それもそのはず、俺は、いつものジャケットを着てはいなかった。今着ているのはダークグリーンのパンツにアイボリーのシャツ、そしてズボンと同系色のベストを着込んでいる。その格好でも一応足元と腰にナイフが仕込んであるところが諜報員の悲しい性というべきか。
「おしゃれだよ。似合う?」
男相手にわざとポーズをとる俺に、パーシヴァルは思いくそヤな顔をしやがった。
「……似合いますけど」
そう言うのが精一杯らしい。
「シャツは借り物だけどね」
「スコット、そういうねたばらしはしない」
む、と俺はスコットを軽く睨む。
「いやみの一つも言いたくなるよ。難しい顔で一時間も居座って。店の雰囲気が悪くなるからやめてほしいんだけど」
「……それは悪かったとは思うが、迷うもんはしょうがないだろう!」
「何で迷ってらっしゃるのですか?」
ひょい、とパーシヴァルがショーケースをのぞいた。
「ピアスを贈ってやろうかと思うんだが、そこの二つのどっちにしようかと迷ってね。片方は瞳の色で、もう片方は服の色なんだ」
「へえ……アメジストの瞳をされてらっしゃるので?」
パーシヴァルのさわやかな笑顔が、一瞬、さわやかではないものへと変わる。
「……反対だ。頼むからお前のところの騎士団長様との仲を勘ぐるのはよしてくれ」
だいたい、この間本命チョコもらってたのはお前だろうに。心の中で毒づくと、パーシヴァルは笑顔の奥の剣呑な光を引っ込めた。
「私の大切にしている花は、香り高いせいか、気をつけてないと害虫が寄ってくるのですよ。その都度駆除しないとね」
「うわあ、さわやかにヤな奴だ」
俺の台詞をパーシヴァルは無視する。
「……とすると、奥方はルビーアイですか。珍しいですね」
「アルビノなんだ。色白だから金よりは銀が……」
「スコット、届け物だよ!」
勢いよく扉が開いたかと思うと、なぜかビッチャムが荷物を抱えて入ってきた。
「お、なんかすごい顔ぶれだな。ほい、注文してた貴金属商品。伝票を確認してくれ」
言って、ビッチャムは包みをゴードンの前に置く。開けると、今入荷してきたばかりのアクセサリーが姿を見せた。
「ビッチャム、お前なんでスコットのところの荷物を?」
「ああ、輸送ルートがグラスランドを横断しててな。うちの連中がその護衛をやってたわけだ」
「なるほどね……あ、これいいな」
伝票を確認するスコットの横から、品物を見ていた俺はつぶやいた。
「そっちの品物で悩んでいたんじゃないの?」
伝票確認を邪魔されて、スコットが嫌そうな顔になる。
「いいじゃねーか。どうせ確認したら店頭に置くんだろ? それ、見せてくれないか?」
言って、俺が指差したのはケースの奥、小さな銀細工の翼に丸い石が下がっているものだった。その石は、水晶のように透き通ってはおらず、その代わりにぽわりとあかりをともしたような、不思議な光を放っている。
「ああ、これは月長石だ。ムーンストーンとも言うけど」
「ムーンストーン? ああ、確かに月光みたいな光り方だな。で、いくらだ?」
デザインもそうだが、石の輝きが気に入った俺はそう尋ねる。スコットは、脇に置いてあった算盤をはじいた。
「仕入れ値から計算すると、これくらいかな」
「……う」
先ほど選んでいた商品よりも、幾分割高なそれに、俺は迷う。
「今仕入れたばかりの品だから、まからないよ」
「うう……」
「折角のホワイトデーなのですから、少し奮発してはいかがですか?」
悩む俺に、パーシヴァルが追い討ちをかけた。
「パーシヴァル、楽しんでるだろ、お前」
「ええ。どちらにしろ、私の財布が痛むわけでもなし」
「なんでこんな腹の黒いのを好きなんだクリスは……」
とほほ、とため息をついて、俺は財布を出した。
「それもらうよ。ぎりぎり予算内だからな。あと、奥にあるリボンをもらえるかな」
「リボン? 包装くらいならサービスでやるけど?」
スコットがピアスを化粧箱に入れながら不思議そうな顔になる。
「いや、この格好だと首に締まりがないから、ネクタイをついでに買おうかと思ってたんだが、今ので予算を使い果たしたからな。リボンで代用だ」
「その歳でリボンタイですか?」
パーシヴァルが呆れる。
「ちっちっち、こういうものは着こなしなのだよパーシヴァル君」
「無駄なあがきのような気も……」
「うるさい男は嫌われるよ」
「別に貴方に嫌われるのは構いません」
男二人の不毛な戦いに、スコットはため息をついている。さっさとどっちか店を出て行って欲しい、そんな感じだ。
「そういうことなら、リボンはサービスにしておきますよ。色は何色がいいですか?」
「奥のダークグリーンのやつ」
「このベルベットリボン? 全く、サービスって言った端から一番高いリボン選ぶんだもんなあ」
「あいそうなのを選んだだけだって」
困った顔のスコットから商品を受け取り、清算をすませると俺はきゅ、とリボンを締めた。鏡を見るが、様になっていないこともない。
「んじゃ、ありがとな」
そのまま、軽い足取りで店を出た。
いい買い物だったな、と珍しくツイている自分に嬉しくなったりしてみる。だが、俺の運もそこまでだった。いいことがあると、その分不幸もやってくるものだ。
「ナッシュ」
声がかかると同時に、首根っこを捕まれた。
「ササライ様……」
振り向くと、姿は少年中身はおやじ、ササライが笑顔で立っている。
「何ちんどん屋みたいな格好してるのさ」
「……ちんどん屋なんて、いまどきの若い人はわかりませんよ?」
「君がわかればそれでいいんじゃない? ところで、ついてきてもらうよ」
有無を言わさず、ササライは俺の服を掴むと歩き出す。いつもならもう少し抵抗するところだが、服が伸びそうなので、早々にそれはあきらめた。
行き先は城の中。恐らく彼の私室だろう。
「書類仕事がたまっててね。手伝ってもらえるかな」
「私は本日休暇中でして」
「休暇手当て出せばいいんだろ? どうせ奥方と逢引するにしたって、やることは夜なんだからいいじゃない」
「……別にそれ目的だけで会ってるわけじゃないんですけどねえ」
相手が女性ならセクハラで訴えられかねない台詞に俺はため息をつく。この上司の暴言には慣れたはずだが、悲しみがこみあげてくるのは何故だろう。
「書類仕事がたまっててさ、今日の馬車でださないと間に合わないんだ」
そう言って、書類の束が渡される。
「それ全部サインして。僕の名前で」
「はあ?」
「あ、内容は把握してるから心配しないで。その枚数全部やったら腱鞘炎になりそうだからさー」
部下が腱鞘炎になるのはいいんですか、というツッコミは聞く気がないらしい。
「俺がササライ様の名前でサインって、まずいんじゃないですか?」
しかも書類の大半には『機密』とか『重要』という判子がべたべたと押してある。これは、見ることもまずいのではないだろうか。
「そういうことに機転がきかないディオスには外で別の仕事をしてもらってるから大丈夫でしょ。なに? あっさりばれるほど、君、人の筆跡まねるの下手だっけ?」
人間として、かなり間違った価値観をお持ちの上司は、平然とそう言い放つ。尚ももごもごと言っていると、とどめの一言が刺さった。
「あんまり作業が遅いと、今日の馬車でないと間に合わない君の経費申請書、意図的に出し忘れるよ?」
神様、そんなに俺が嫌いですか。
俺は思わず祈った。
「畜生……何が夜までには終わる、だ」
深夜、やっと上司の命令の山を片付けた俺は自室の戸を開けた。時計を見ると、あと十分でホワイトデー終了である。当然、部屋には誰もいない。
「……そんな長々と待ってくれるわけ、ないよなあ」
今から探しに行こうとしてももう遅いし、大体、今日一日働かされたおかげで体はくたくたである。昼はぱりっとしていた洋服も、ほこりをかぶってよれよれになっている。
「まいったな」
言って、俺は床に座り込み、ベッドにもたれかかった。
ここ数日の努力がすべてふいになり、気分が落ち込む。本気で転職を考えてやろうか、とできもしないことをつらつらと思っていると、部屋の戸が開いた。
「いつにも増してくたびれておるのう」
「シエラ!」
戸口には、来訪するはずのない女性が立っていた。俺は慌てて立ち上がる。今の今まで、もう一歩も動きたくないと悲鳴をあげていた体が、彼女を見たとたん素直に動くのだから、現金なものである。
「なんで……待っていてくれたのか?」
「そうでもない。昨日ササライが嬉々として仕事を増やしておったからこんなことじゃろうと見当をつけておったのじゃ」
「……だったらその時点でササライを止めてくれよ」
「面倒くさい」
きっぱり言い切って、シエラはベッドに座った。俺は力が抜けていく膝になんとか力を入れる。今日、ころあいを見計らって訪れるくらいはしてくれたのだ。いつもの彼女から考えてみれば、まだ気を遣っているほうだ。
ため息一つでそれを押し流す。
「ああもう、どうでもいいや。とにかくあんたに会えたんだし。これ、この間のお返しだ。受け取ってくれるだろう?」
「うむ」
ピアスの入った箱を、シエラは満足そうに受け取る。そして、包みを開け始めた。それを見ながら俺は用意しておいたワインの栓を抜きにかかる。
「どうだ?」
「ふふ……またかわいらしいものを」
口元に浮かぶ微笑を見て、俺も笑った。贈り物が喜ばれると、やっぱり嬉しい。
「たいしたものは贈ってないというのに、また随分と頑張ったものじゃのう」
「それだけ嬉しかったってことさ」
暗に、『来年も贈ってくれると嬉しいなあ』と主張してみたが、シエラはそれを微笑みで受け流しやがった。そう簡単に約束を取り付けてくれる女じゃあない。
「ん」
シエラはずい、とピアスの入った化粧箱を俺に差し出した。突っ返す、というのではない。つけろということだろう。
ワインを注いでいたグラスを横におき、ピアスを箱からとってつけてやると、ムーンストーンはその幻想的な光でもってシエラの耳を飾った。やっぱりこれを選んで正解だったな、と俺は悦にいる。
「にやけた顔をしおって……しまりがないぞえ?」
「あんたのそんな様子をみてにやけない男がいたらそっちのほうが変だと思うね」
「口の減らぬ男じゃ」
だいたい、そのにやけた男の顔を見て、優越感を感じているのはどこのどちら様でしょうねえ。言ったら殴られるから言わないけど。
ワインをテーブルに置き、俺はシエラの横に座る。シエラはそれを見上げると、手を首元に伸ばしてきた。
「おや、ここにももう一つプレゼントがある」
指を絡めてきたのは、昼間結んだリボンタイ。結びなおしてないからもうよれよれだった。そういえば、リボンがついているのだから、これだってプレゼントと言えなくもない。
「どうぞ、お納めくださいシエラ様……といってもコレは十五年も前から貴方のものですが」
わざときざな台詞を吐いてみても、この格好じゃ迫力不足だったらしい。シエラはそれを笑うと、リボンに手をかけた。しゅるりと解くと、シャツのボタンも数個外す。俺の首筋にシエラの吐息がかかり、肩口に彼女の指が滑り、そして……。
がぷ。
食いつかれた。
……ああ、そうだよな! あんたはそういう女だよな!!
牙をたてられた痛みと、軽い貧血にさいなまれながら、俺は悲しい気持ちになる。
久しぶりにシエラから誘ってきたかと思うと、こういうオチかよ!
「シエラ……血を吸うときは、せめて一言断ってくれよ」
「なんじゃ、よいと言ったのはおんしであろう」
シエラが、首筋から口を離す。
「……そうだけどさ」
たまには別の期待をしたっていいじゃないか。
「あんしんせい」
ぺろり、とまだ血の流れる俺の首をシエラが舐めた。
「こちらも一緒に食してやろうほどに」
唇を鎖骨へ移動させながら体重をかけられ、俺はベッドに倒れこむ。しなやかな猫科の動物のような仕草で、シエラは俺を組み敷いた。
「あ……シエラ」
「ふふ」
そのまま俺はシエラに『食われた』。
翌日。
パーシヴァル・フロイライン卿は、いつものように練兵場へと足を運んでいた。少々寝不足で目が赤いが、恋人との逢瀬を楽しんだ代償なのだから自業自得だ。城を出ようとしたところで、少女とすれ違う。と、何かが腕にひっかかった。
「きゃっ」
慌てて見ると、少女の髪が甲冑の腕の止め具にひっかかったらしい。
「すみません、レディ。いま外しますから少々お待ちを……」
髪を外すために、手甲を外す。少女が少し涙目になってこちらを見上げてきた。それを見て、パーシヴァルは少し面食らう。
(こんなに綺麗な子が、この城にいたのか)
恋人のものより、更に色素の薄い銀髪に、大きなルビーアイ。白磁の肌は透き通るようで、花びらのような唇が愛らしい。
十五六、という幼い年頃が射程範囲外だが、五年後が楽しみ、といった感じである。
「はい、取れましたよ。申し訳ありませんでした」
髪をとってやり、丁寧に謝ると、少女は笑った。
「いえ、お気になさらず」
そう言って、踵を返す。同時に、ふわりと銀の髪が舞い上がった。
「……? ……っ!」
髪の間からのぞいた小さなピアスを見て、パーシヴァルは固まった。
立ち去っていく彼女の耳を彩っていたあの飾りは、まぎれもなく、昨日ナッシュが買っていったものだ。スコットの話では一点ものだそうだから、同じものは売られていない。それに、ルビーアイと白い肌。
「……ナッシュ、殿?」
昨日のあの男の浮かれようを思い出す。それは、本気で好きな女にプレゼントを買っているようだった。だが。
だがしかし。
「あれは犯罪だろう……」
パーシヴァルがそうつぶやいたのはいっそ当然といえよう。
